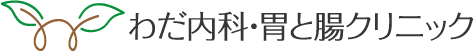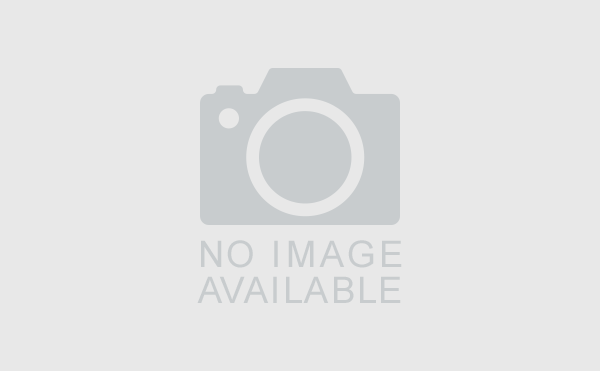小児の過敏性腸症候群の選択肢。小建中湯とは?
大分県大分市のわだ内科・胃と腸クリニック院長の和田蔵人(わだ くらと)です。
「学校に行く前になると決まってお腹が痛くなる」「検査をしても異常なしと言われるのに、腹痛や下痢を繰り返す」…そんなお子さんのつらい症状に、ご家族も心を痛めているのではないでしょうか。その不調は、単なる食べ過ぎや風邪ではなく、ストレスに敏感な子どもに多い「過敏性腸症候群(IBS)」かもしれません。
実は、子どものお腹の不調の背景には、テストのプレッシャーや友人関係といったストレスと、発達途中にある繊細な体が複雑に影響しています。それは、お子さんの心が発している「SOSサイン」とも言えるのです。
この記事では、小児の過敏性腸症候群の根本原因を紐解きながら、西洋薬とは異なるアプローチで心と体の両面から体質改善を目指す漢方薬「小建中湯」について詳しく解説します。お子さんの笑顔を取り戻すためのヒントが、きっと見つかるはずです。
もしかして過敏性腸症候群?小児に多いお腹の不調3つの原因
「最近、うちの子がよくお腹を痛がるようになった」 「学校に行く前になると、決まってトイレに駆け込んでいる」
お子さんのお腹の不調が続くと、保護者の方も心配になりますよね。病院で血液検査やエコー検査をしても「特に異常はありません」と言われるのに、腹痛や下痢、便秘を繰り返す。
このような場合、「過敏性腸症候群(IBS)」という病気の可能性があります。子どものお腹の不調は、単なる食べ過ぎや風邪だけが原因ではありません。背景には、子ども特有の繊細な心と、発達途中にある体の状態が複雑に影響しています。ここでは、小児の過備性腸症候群につながりやすい、3つの主な原因を詳しく解説します。
登校前やテスト前に悪化する腹痛・下痢・便秘
過敏性腸症候群の大きな特徴は、特定の状況で症状が悪化する点です。特に、学校生活に関連する心理的なプレッシャーがかかる場面で、お腹の不調を訴えるお子さんは少なくありません。これは、心の緊張が体にサインとして現れている状態です。
お子さんに、このような場面で症状は出ていませんか?
- 登校前の朝「学校に行きたくない」という気持ちだけでなく、実際に差し込むような腹痛が起きたり、何度もトイレに行きたくなったりする。
- テストや発表会の前強い緊張や不安を感じると、急にお腹がゴロゴロと鳴り出し、下痢や急な便意に襲われる。
- 授業中や静かな場所お腹の音やガスが気になってしまい、その不安からさらに症状が悪化してしまう。
- 習い事や部活動の前後サッカーの試合前のようなプレッシャーを感じる場面や、活動後の疲労が溜まったときにお腹の調子を崩す。
これらの症状は、決して仮病や気のせいではありません。私たちの脳と腸は「脳腸相関」といって、自律神経などを介して密接に情報をやり取りしています。脳がストレスを感じると、その情報が腸に伝わり、腸の動きが過剰になったり、逆に鈍くなったりします。お子さんが特定の状況でお腹の不調を訴えるときは、その背景にある心理的な負担にも目を向けることが大切です。
ストレスが引き金となる自律神経の乱れ
私たちの体には、自分の意思とは関係なく内臓の働きや体温などを調整してくれる「自律神経」という仕組みがあります。自律神経は、心と体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」から成り立っています。この2つが車のアクセルとブレーキのようにバランスを取り合うことで、私たちの健康は保たれています。
| 神経の種類 | 主な働き | 腸への影響 |
|---|---|---|
| 交感神経 | 緊張・興奮しているときに働く(アクセル役) | 腸の動きを抑える、または異常に動かす |
| 副交感神経 | リラックスしているときに働く(ブレーキ役) | 腸の動きを穏やかにし、消化を助ける |
しかし、子どもたちが日々直面するさまざまなストレスによって、このバランスは簡単に崩れてしまいます。学校での勉強やテスト、友人関係の悩み、先生との関係、習い事のプレッシャーなど、大人が思う以上に子どもは多くのストレスにさらされています。
慢性的なストレスは交感神経を過剰に働かせ続けます。その結果、腸の動きに異常が生じ、腹痛や下痢、便秘といった過敏性腸症候群の症状を引き起こすのです。つまり、お腹の症状は、お子さんの心が発している「SOS」のサインであるとも考えられます。
虚弱体質と消化機能の未熟さ
ストレスのような外的な要因だけでなく、お子さん一人ひとりが持つ体質も、お腹の不調と深く関係しています。特に、東洋医学で「虚弱体質」と表現されるような、エネルギーが不足しがちな体質のお子さんは、過敏性腸症候群になりやすい傾向があります。
お子さんの体質をチェックしてみましょう
- ☐ 風邪をひきやすく、一度ひくと長引きやすい
- ☐ 疲れやすく、外で元気に遊ぶ時間が短い
- ☐ 食が細く、食べるのに時間がかかる
- ☐ 顔色があまり良くなく、目の下にクマができやすい
- ☐ 年齢のわりに小柄で、体重がなかなか増えない
- ☐ 手足が冷たいことが多い
また、子どもの消化器官はまだ発達の途中であり、大人に比べて機能が十分に成熟していません。そのため、少しの体調変化や食事の乱れでも、お腹の調子を崩しやすいのです。
特に、冷たい飲み物や食べ物、お菓子やインスタント食品の摂りすぎは、未熟な胃腸に大きな負担をかけます。もともとの体の弱さと未熟な消化機能という土台があるところに、ストレスが加わることで、過敏性腸症候群の症状が発症・悪化しやすくなります。症状の改善には、ストレスへの対処と同時に、体の内側から胃腸を丈夫にしていくアプローチが非常に重要になります。
小建中湯が持つ4つの働きと効果的な子どもの体質
お子さんの繰り返すお腹の不調は、ご家族にとっても大きな心配事ですよね。 「何か悪い病気なのでは?」と不安になることもあるでしょう。
西洋医学の検査で異常が見つからない場合、漢方治療が有効な選択肢となることがあります。 特に「小建中湯(しょうけんちゅうとう)」は、小児の過敏性腸症候群のようなお腹の不調に対して、古くから用いられてきた代表的な漢方薬です。
小建中湯は、単に腹痛や下痢を抑えるだけでなく、お子さんの繊細な心と体のバランスを整え、不調が起こりにくい体質へと導くことを目的としています。 ここでは、小建中湯が持つ働きと、どのような体質のお子さんに効果が期待できるのかを、医師の視点から詳しく解説します。
お腹を温めて痛みを和らげる作用
「冷たいものを飲むと、すぐにお腹が痛くなる」 「お腹を手で温めると、少し痛みが楽になる」
お子さんにこのような傾向はありませんか。 これは、お腹が内側から冷えることで胃腸の血行が悪くなり、腸の筋肉が異常に緊張して、けいれん性の痛みを引き起こしている状態です。
小建中湯には、体を温める働きを持つ生薬がバランス良く配合されています。
- 桂枝(けいし)・生姜(しょうきょう)
- 体の芯からじんわりと温め、胃腸の血流を改善します。
- 芍薬(しゃくやく)
- 筋肉の過度な緊張をゆるめ、差し込むような痛みを和らげる働きがあります。
これらの生薬が協力し合うことで、冷えが原因で起こる腹痛やお腹の張りを根本から改善していきます。 東洋医学では、体が冷えて機能が低下した状態を「虚寒証(きょかんしょう)」と呼びますが、小建中湯はまさにこの状態を改善するのに適した漢方薬です。
胃腸の働きを整え気力と体力を補う
過敏性腸症候群のお子さんには、もともと食が細かったり、疲れやすかったりといった「虚弱体質」が見られることが少なくありません。 東洋医学では、この状態を「脾虚(ひきょ)」と呼びます。
「脾」とは、西洋医学の脾臓(ひぞう)だけを指すのではなく、飲食物を消化し、栄養を吸収してエネルギーに変える消化器系全体の働きを意味します。 つまり「脾虚」とは、消化吸収システムが弱り、生命活動に必要なエネルギー(気)を十分に作り出せない状態のことです。
小建中湯は、その名の通り「中(体の中心である胃腸)を建て直す」ことを最も得意とする漢方薬です。 中心的な役割を果たすのが「膠飴(こうい)」という生薬です。 これは麦芽から作られた水あめで、消化しやすく、すぐにエネルギー源となるため、弱った胃腸に負担をかけることなく栄養を補給できます。
以下のチェックリストに当てはまる項目が多いお子さんは、小建中湯が特に合いやすい体質と考えられます。
【小建中湯が合いやすいお子さんのサイン】
- ☐ もともと食が細く、食べるのに時間がかかる
- ☐ 疲れやすく、すぐに「疲れた」と言ったり横になったりする
- ☐ 顔色が悪く、特に目の下に青白いクマができやすい
- ☐ まつ毛が長い傾向がある
- ☐ お腹の皮膚が薄く、血管が透けて見えることがある
- ☐ 手足が冷たいことが多い
- ☐ 風邪をひきやすく、一度ひくと長引きやすい
小建中湯は、弱った胃腸の働きを助けながら気力と体力を補います。 その結果、お腹の調子を整えるだけでなく、疲れにくい元気な体づくりをサポートします。
イライラや不安を落ち着かせる効果
前の章でも触れましたが、私たちの脳と腸は「脳腸相関」によって密接につながっています。 学校のテストや友人関係の悩みといった精神的なストレスが、自律神経のバランスを乱し、直接お腹の症状として現れることは、お子さんによく見られる現象です。
小建中湯は、お腹の働きを整えるだけでなく、繊細でデリケートな子どもの心を穏やかにする効果も期待できます。
- 桂枝(けいし)・大棗(たいそう)
- 高ぶった神経を鎮め、精神的な緊張や不安感を和らげる働きがあります。
ストレスによって乱れがちな心と体のバランスを優しく整えることで、過敏になった腸の反応を抑えていきます。 そのため、「登校前になると決まってお腹が痛くなる」といった、特定の状況で症状が悪化するお子さんにも非常に適しています。
西洋薬との違いと漢方治療のメリット
お腹の症状に対する治療では、西洋薬と漢方薬のどちらか一方を選ぶ必要はありません。 それぞれの長所を理解し、お子さんの状態に合わせて使い分けることや、併用することが大切です。
| 比較項目 | 西洋薬 | 漢方薬(小建中湯) |
|---|---|---|
| 治療の目的 | 今ある症状をピンポイントで抑える | 症状が出にくい心と体づくり(体質改善) |
| アプローチ | 対症療法(下痢止め、痛み止めなど) | 全身のバランスを整える根本的な治療 |
| 得意なこと | 急で強い症状を素早く緩和すること | 慢性的な不調や体質的な弱さの改善 |
| 効果の範囲 | 胃腸の症状に限定的 | 腹痛改善に加え、疲労感や冷え、精神不安など全身状態の改善も期待できる |
漢方治療の大きなメリットは、症状の背景にある「虚弱体質」や「冷え」「精神的なストレス」といった根本原因に目を向ける点にあります。
そのため、小建中湯を服用することで、お腹の調子が良くなるだけでなく、
- 風邪をひきにくくなった
- 疲れにくく元気になった
- 朝、起きられるようになった
といった、全身の状態が改善するケースも少なくありません。 一人ひとりのお子さんの体質に合わせたオーダーメイドの治療ができること、そして心と体の両面からアプローチできることが、漢方治療の大きな強みです。
子どもが嫌がらない漢方薬の飲ませ方のコツ
「漢方薬は苦くて飲みにくそう」というイメージがあるかもしれません。しかし、小建中湯は「膠飴(こうい)」という水あめのような甘い生薬が含まれているため、漢方薬の中では比較的飲みやすいのが特徴です。
それでも味が苦手なお子さんのために、上手に飲んでもらうためのコツをいくつかご紹介します。
【味や香りを変える工夫】
- 甘いものに混ぜる チョコレート味やココア味のアイスクリーム、プリン、ヨーグルトなどがおすすめです。 ココアやミロ、メープルシロップなどに混ぜるのも良い方法です。 ※1歳未満のお子さんにはハチミツを与えないでください。
- 服薬補助ゼリーを使う 薬局などで手に入る、薬を飲みやすくするための専用ゼリーを使うのも有効です。味のバリエーションも豊富です。
- 少量の水で練ってお団子にする 粉薬を数滴の水で練って小さなお団子状にします。 それを頬の内側や上あごに貼り付け、水やお茶を飲ませると、 味を感じにくく、スムーズに飲み込めます。
何よりも大切なのは、無理強いしないことです。「これを飲んだらお腹が元気になるお守りだよ」と前向きな言葉をかけ、上手に飲めた時はたくさん褒めてあげましょう。「お薬が飲めた」という成功体験が、お子さんの治療への意欲につながります。
家庭でできる食事療法とストレスを減らす工夫
お薬での治療と合わせて、ご家庭での食事や生活習慣を見直すことで、症状の改善や再発予防が大きく期待できます。できることから、一つずつ試してみてください。
1. お腹にやさしい食事を心がける 胃腸の働きが弱っているときは、「消化が良く、お腹を温める食事」が基本です。
| おすすめの食事 | 避けたほうがよい食事 |
|---|---|
| 体を温める食材 しょうが、ねぎ、かぼちゃ、鶏肉など | 冷たいもの アイスクリーム、冷たいジュースなど |
| 消化の良い炭水化物 おかゆ、うどん、よく煮込んだ野菜など | 脂っこいもの 揚げ物、スナック菓子、脂肪の多い肉など |
| 温かい汁物 具だくさんの味噌汁や野菜スープなど | 刺激の強いもの 香辛料、炭酸飲料など |
2. 生活リズムで自律神経を整える 早寝早起きを心がけ、毎日決まった時間に食事をとるようにしましょう。規則正しい生活は、乱れがちな自律神経のバランスを整える土台となります。 特に、朝食をしっかり食べることは、腸の働きを活発にするための大切なスイッチです。寝る前のスマートフォンやゲームは脳を興奮させてしまうため、控えるようにしましょう。
3. 安心できる「安全基地」をつくる ストレスは症状を悪化させる大きな原因です。習い事などで忙しすぎないか生活スケジュールを見直し、お子さんが心からリラックスできる時間を確保してあげてください。
学校での出来事をじっくり聞くなど、お子さんの話に耳を傾ける時間を大切にしましょう。 このとき、アドバイスをするよりも、まずはお子さんの気持ちに共感することが重要です。 「お家はいつでも味方で、安心できる場所だ」とお子さんが感じられる環境を作ってあげることが、何よりのサポートになります。
まとめ
今回は、お子さんの過敏性腸症候群の原因と、漢方薬「小建中湯」について解説しました。
繰り返すお腹の不調は、学校生活でのストレスや、お子さん自身の繊細な体質が深く関係しています。小建中湯は、単に痛みを和らげるだけでなく、弱った胃腸を丈夫にし、心を穏やかにすることで、症状が起こりにくい体質へと導くお薬です。
お薬での治療とあわせて、ご家庭での食事や生活習慣の工夫も大切になります。お子さんのお腹のことでお悩みの際は、一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。心と体の両面から、一緒に最適なサポートを探しましょう。