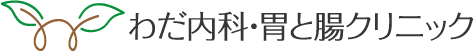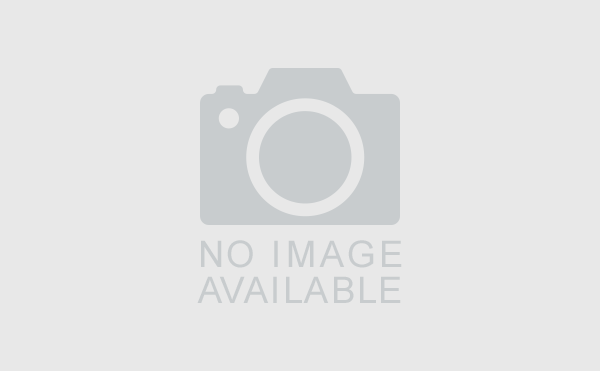“ノンアルなら大丈夫”は本当か? 肝機能異常の人が知っておくべき真実とは?
大分県大分市のわだ内科・胃と腸クリニック院長の和田蔵人(わだ くらと)です。あなたは、健康診断で肝機能の数値が気になったり、何となくだるさを感じたりしていませんか?もしかしたら、それは肝臓からのSOSかもしれません。多くの人が「ノンアルコール飲料なら肝臓に優しい」と考えているようですが、実は落とし穴があることをご存知でしょうか?
1999年の調査では、肝機能障害の患者数は約40万人でしたが、2020年には150万人に増加。実に約4倍もの増加です。現代社会のストレスや食生活の変化が、肝臓に大きな負担をかけていることが分かります。今回は、ノンアルコール飲料と肝臓の関係という知られざる真実に迫ります。種類ごとの特徴や成分、そして肝臓への影響を詳しく解説することで、本当に「大丈夫」な飲み物選びをサポートします。もしかしたら、あなたの健康を左右する重要な情報が隠されているかもしれません。
ノンアルコール飲料と肝臓の関係:知っておきたい真実
健康診断で肝機能の数値が引っかかったり、何となくだるさを感じたりすると、お酒を控える方も多いのではないでしょうか。そんな時、お酒の代わりにノンアルコール飲料を選ぶ方が増えています。
「ノンアルコールなら肝臓に良いはず」と考えている方もいるかもしれません。本当にそうでしょうか?この記事では、ノンアルコール飲料と肝臓の関係について、種類や成分、選び方、注意点などを詳しく解説します。

ノンアルコール飲料の種類と特徴
ノンアルコール飲料は、大きく分けて「ノンアルコールビールテイスト飲料」「ノンアルコールワインテイスト飲料」「ノンアルコールカクテルテイスト飲料」などに分類できます。
| 種類 | 特徴 | 原材料の例 |
|---|---|---|
| ノンアルコールビールテイスト飲料 | ビールのような風味を楽しめる | 麦芽、ホップ |
| ノンアルコールワインテイスト飲料 | ワインのような風味を楽しめる | ぶどう果汁、香料 |
| ノンアルコールカクテルテイスト飲料 | カクテルのような風味を楽しめる | 果汁、香料、酸味料 |
特にノンアルコールビールテイスト飲料は種類が豊富で、「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」「カロリーオフ」など、様々なタイプから選ぶことができます。
ノンアルコール飲料に含まれる成分と肝臓への影響
ノンアルコール飲料はアルコールをほとんど含んでいないため、アルコール性肝障害のリスクは低いと考えられています。筑波大学の研究では、ノンアルコール飲料を提供することで、飲酒量が有意に減少することが示されました。これは、ノンアルコール飲料がアルコール飲料の代わりに利用できることを示唆しています。
しかし、ノンアルコール飲料だからといって安心はできません。ノンアルコール飲料にも様々な成分が含まれており、肝臓への影響は様々です。
例えば、甘味料として使用されるアセスルファムKは、過剰摂取により肝臓に負担をかける可能性が指摘されています。また、一部の商品にはプリン体や糖質が含まれており、肝機能が気になる方は注意が必要です。これらの成分が、脂肪肝や肝機能の数値悪化につながる可能性も否定できません。
肝機能への影響が少ないノンアルコール飲料の選び方
肝機能への影響を少なくするためには、ノンアルコール飲料を選ぶ際に以下の4つのポイントに注意しましょう。
- アルコール度数0.00%のもの:微量のアルコールでも、毎日摂取することで肝臓への負担が蓄積する可能性があります。
- 添加物を確認:アセスルファムK、カラメル色素、安息香酸Naなどの添加物は、過剰摂取により肝臓に負担をかける可能性があります。無添加、または添加物が少ないものを選びましょう。
- 糖質、プリン体、カロリーをチェック:糖質やプリン体は、肝臓での代謝に負担をかける可能性があります。カロリーが高いと、脂肪肝のリスクを高める可能性も懸念されます。肝機能が気になる方は、これらの含有量が少ない、あるいはゼロのものを選びましょう。
- 機能性表示食品や特定保健用食品を選ぶ:特定の保健の用途に資することを目的として表示を行う食品であり、消費者庁長官の個別審査を受けた上で許可表示されたものです。科学的根拠に基づいて健康への効果が認められた商品なので、安心して飲むことができます。
ノンアルコール飲料の適切な摂取量と注意点
ノンアルコール飲料であっても、飲みすぎは禁物です。過剰摂取は糖質や添加物の摂りすぎにつながり、肝臓だけでなく他の臓器にも負担がかかります。
肝機能が低下している方は特に摂取量に注意が必要です。一度に大量に飲むのではなく、少量ずつ、時間を空けて飲むようにしましょう。また、健康診断の前日や当日は、糖質を含むノンアルコール飲料の摂取は控えましょう。
妊娠中や授乳中の方は、ノンアルコール飲料であっても、医師や薬剤師に相談してから飲むようにしてください。
肝機能異常・障害の基礎知識:原因・症状・検査
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、初期段階では自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、異常に気づいたときには、病気がかなり進行しているケースも少なくありません。
しかし、肝臓は生命維持に不可欠な臓器です。肝臓の役割を理解し、肝機能異常のサインを見逃さないようにすることが大切です。この章では、肝機能異常・障害の基礎知識として、主な原因、症状、検査方法について解説します。

肝機能異常・障害の主な原因5つ
肝機能異常・障害の原因は多岐にわたりますが、代表的なものを5つ紹介します。
- **ウイルス性肝炎:**A型、B型、C型など、様々な種類のウイルスが原因で肝臓に炎症が起こる病気です。ウイルスへの感染経路は、ウイルスごとに異なります。例えば、A型肝炎は経口感染、B型・C型肝炎は血液を介した感染で発症します。
- **アルコール性肝障害:**過度なアルコール摂取により、肝臓に障害が起こる病気です。アルコールは肝臓で分解されますが、過剰に摂取すると肝臓への負担が大きくなり、炎症や脂肪蓄積を引き起こします。
- **脂肪肝:**肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態です。大きく分けて、アルコールの過剰摂取が原因となる「アルコール性脂肪肝(AFLD)」と、それ以外の原因による「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」の2つに分類されます。NAFLDは、肥満や糖尿病、高脂血症といった生活習慣病と深く関連しています。
- **自己免疫性肝炎:**自身の免疫システムが誤って肝臓を攻撃してしまう病気です。原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境要因などが関わっていると考えられています。
- **薬剤性肝障害:**特定の薬剤の服用によって肝臓に障害が起こる病気です。薬は肝臓で代謝されるため、特定の薬剤が原因で肝機能に影響が出ることがあります。
肝機能の数値(AST、ALT、γ-GTPなど)の見方
肝機能検査では、血液検査で肝臓の状態を調べます。血液中に含まれる様々な酵素の値を測定し、肝臓の細胞が損傷を受けていないかを確認します。代表的な数値として、AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)、ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)、γ-GTP(ガンマグルタミルトランスペプチダーゼ)などがあります。
これらの酵素は、健康な状態では肝細胞内に存在していますが、肝細胞が損傷すると血液中に漏れ出てきます。そのため、これらの数値が高いほど、肝機能の異常が疑われます。
- **AST:**肝臓以外にも心臓や筋肉など、様々な臓器に存在する酵素です。そのため、ASTの数値が高いからといって、必ずしも肝機能の異常を示すとは限りません。
- **ALT:**主に肝臓に存在する酵素です。肝臓の炎症の程度を反映するため、肝機能の状態を評価する上で重要な指標となります。
- **γ-GTP:**肝臓や胆道に存在する酵素です。アルコールの影響を受けやすく、数値が高い場合はアルコール性肝障害の可能性が考えられます。
これらの数値は、基準値と比較することで肝機能の状態を評価します。基準値は検査機関によって多少異なる場合がありますが、一般的にはASTとALTは10~30 U/L、γ-GTPは男性で10~70 U/L、女性で10~40 U/L程度です。
ただし、数値が基準値を超えていても、必ずしも病気を意味するわけではありません。医師は、他の検査結果や症状なども総合的に判断して診断を決定します。
肝機能異常・障害の初期症状と進行した場合の症状
肝機能異常・障害の初期症状は自覚しにくいものが多く、疲れやすい、食欲不振、吐き気、消化不良などが挙げられます。これらの症状は他の病気でも見られることが多いため、見過ごしてしまう可能性も高いです。
しかし、放置すると黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹水(お腹に水がたまる)、肝性脳症(意識障害や精神症状が現れる)といった重篤な症状が現れる可能性があります。さらに、肝硬変や肝がんへと進行するリスクも高まります。
初期症状が軽いからといって油断せず、少しでも異変を感じたら医療機関を受診することが大切です。
肝機能検査の種類と費用
肝機能検査は、主に血液検査で行われます。血液検査では、AST、ALT、γ-GTPなどの酵素の値の他に、アルブミンやビリルビンなどの数値も測定し、肝臓の状態を総合的に評価します。
費用は医療機関によって異なりますが、血液検査の場合は3,000円~5,000円程度が相場です。必要に応じて、超音波検査やCT検査などの画像診断を行う場合もあります。これらの検査は血液検査よりも費用が高くなる傾向があり、超音波検査で5,000円~10,000円程度、CT検査で10,000円~20,000円程度が目安です。
わだ内科・胃と腸クリニックでの肝機能検査について
わだ内科・胃と腸クリニックでは、肝機能に関する様々な検査を実施しています。血液検査はもちろんのこと、超音波検査など、患者さんの状態に合わせた最適な検査方法をご提案いたします。検査結果に基づいて、丁寧な説明と適切な治療方針をご提示いたしますので、肝機能にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
肝機能を改善するための生活習慣:食事・運動・休養
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、初期段階では自覚症状が現れにくい臓器です。健診で肝機能の数値が悪かった、という結果を突きつけられて初めて肝臓の異常に気づく方も少なくありません。
まるでマラソンランナーのように、休むことなく働き続ける肝臓は、私たちの体にとって非常に重要な役割を担っています。肝臓が受けたダメージを修復し、機能を改善するためには、日々の生活習慣の見直しが欠かせません。食生活、運動習慣、そして休養。この3つの基本的な生活習慣を改善することで、肝臓の健康を守り、毎日をより元気に過ごせるようになるでしょう。

肝臓に良い食べ物と悪い食べ物
肝臓の健康を維持するには、バランスの取れた食事が重要です。肝臓に良い栄養素を積極的に摂り、負担となる食品を控えることで、肝機能の改善をサポートできます。
肝臓に良い食べ物
- **良質なたんぱく質:**肝臓の細胞の修復や再生には、たんぱく質が不可欠です。たんぱく質は、肉、魚、卵、大豆製品など、様々な食品から摂ることができます。これらの食品をバランス良く取り入れることで、肝臓の再生を促し、健康な状態を維持することができます。たんぱく質が不足すると、肝臓の再生が遅れ、肝機能の低下につながる可能性があります。
- **ビタミン・ミネラル:**ビタミンやミネラルは、肝臓の働きを助ける重要な栄養素です。これらの栄養素は、緑黄色野菜、果物、海藻類などに豊富に含まれています。例えば、ビタミンAは肝臓の細胞の再生を促進し、ビタミンCは肝臓の解毒作用をサポートします。ミネラルの中でも、鉄は肝臓の酵素の働きを助ける役割を担っています。
- **食物繊維:**食物繊維は、腸内環境を整えることで、肝臓の負担を軽減する効果が期待できます。食物繊維は、きのこ類、海藻類、穀物などに多く含まれています。食物繊維を摂取することで、腸内環境が改善され、有害物質の発生や吸収が抑えられます。その結果、肝臓の解毒作用の負担が軽減され、肝機能の維持に役立ちます。
肝臓に悪い食べ物
- **過剰な脂肪:**脂肪の摂りすぎは、肝臓に中性脂肪が蓄積し、脂肪肝の原因となる可能性があります。揚げ物や脂身の多い肉などは控えめに摂取するようにしましょう。脂肪肝は、肝機能の低下だけでなく、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを高める可能性があります。
- **アルコール:**アルコールは肝臓で分解されますが、過剰に摂取すると肝臓に大きな負担がかかります。アルコールの分解過程で発生するアセトアルデヒドは、肝細胞を傷つけ、炎症を引き起こす原因となります。長期間にわたる過剰なアルコール摂取は、アルコール性肝炎や肝硬変といった深刻な肝臓病につながる可能性があります。ノンアルコール飲料でも、糖質を多く含むものは、中性脂肪を増やし、肝臓に負担をかける可能性があるため、飲み過ぎには注意が必要です。
- **添加物:**加工食品などに含まれる食品添加物は、肝臓で解毒され、その過程で肝臓に負担がかかります。特に、アセスルファムK、カラメル色素、安息香酸Naなどの添加物は、過剰摂取により肝臓への負担を増大させる可能性があるため注意が必要です。できるだけ自然な食品を選び、添加物の摂取量を減らすように心がけましょう。
肝機能改善に効果的な運動方法
適度な運動は、肝機能の改善に効果的です。ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動は、肝臓への血流を促進し、脂肪の燃焼を助けるため、脂肪肝の予防や改善にもつながります。1回30分程度の運動を週に3回以上を目標に、無理なく続けられるように、ご自身のペースで取り組んでみましょう。運動習慣がない方は、まずは軽いウォーキングから始めて、徐々に運動量を増やしていくと良いでしょう。
肝臓の機能を助けるための休養の重要性
肝臓は、睡眠中に修復や再生を行うため、十分な睡眠をとることは肝機能の維持に不可欠です。睡眠不足が続くと、肝臓の修復が十分に行われず、肝機能の低下につながります。毎日7時間程度の質の良い睡眠を確保するように心がけましょう。睡眠の質を高めるためには、寝る前にカフェインを摂取しない、寝室を暗く静かに保つ、規則正しい生活リズムを維持するなどの工夫が有効です。
ストレス軽減と肝機能の関係
ストレスは自律神経のバランスを崩し、肝臓の働きにも悪影響を及ぼす可能性があります。ストレスを軽減するための工夫も大切です。趣味やリラックスできる活動、適度な運動など、ご自身に合ったストレス解消方法を見つけて、心身ともに健康な状態を保ちましょう。ストレスを溜め込まず、上手に発散することが、肝臓の健康維持にもつながります。
わだ内科・胃と腸クリニックへのアクセスと診療案内
大分市津守にある「わだ内科・胃と腸クリニック」では、肝機能異常をはじめ、内科、消化器内科、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)など、幅広い診療科目で地域医療に貢献しています。肝機能検査をご希望の方や、肝臓に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。アクセス方法や診療時間、予約方法などの詳細は、クリニックのウェブサイトをご覧ください。
まとめ
ノンアルコール飲料は、肝機能異常がある方にとって、完全に安全と言えるのでしょうか? この記事では、ノンアルコール飲料の種類や成分、肝臓への影響、選び方などを詳しく解説しました。ノンアルコール飲料を選ぶ際には、アルコール度数0.00%であること、添加物を確認すること、糖質やプリン体、カロリーをチェックすること、機能性表示食品や特定保健用食品を選ぶことなど、いくつかのポイントがあります。 また、飲みすぎは禁物です。少量ずつ、時間を空けて飲むようにし、健康診断の前や妊娠中、授乳中の方は特に注意が必要です。肝機能を改善するためには、バランスの良い食事、適度な運動、十分な休養、そしてストレス軽減も大切です。 少しでも肝臓の健康に不安を感じたら、専門医に相談してみましょう。
参考文献
- Yoshimoto H, Kawaida K, Dobashi S, Saito G, Owaki Y. Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: A randomized controlled study.