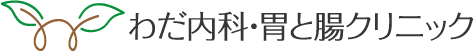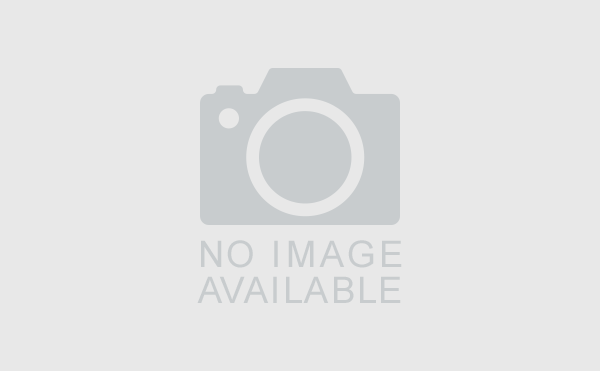ラズベリー様胃がんのお話
「ラズベリー様胃がん」という病名を聞いたことはありますか?実はこのがんは、ピロリ菌のいない“きれいな胃”に発生する新しいタイプのがんとして近年注目されています。「ピロリ菌を除菌したから、もう安心」―そう考えていた方にとっては、大きな驚きかもしれません。
しかし、過度に心配する必要はありません。このがんは進行が非常に緩やかで、転移の報告もほとんどない、おとなしい性質を持っているからです。多くは5mm以下と非常に小さく、自覚症状がないまま発見されることがほとんどです。
この記事では、ラズベリー様胃がんの正体から、体に負担の少ない最新の内視鏡治療までを詳しく解説します。
ラズベリー様胃がん(腺窩上皮型胃腫瘍)の3つの主な特徴
胃カメラ検査で「ラズベリー様胃がんの疑い」と告げられると、聞き慣れない病名に大きな不安を感じてしまうことでしょう。
この病気は、胃の粘膜の表面にある「腺窩(せんか)」という、胃液などを分泌する小さなくぼみから発生する腫瘍です。近年、胃がんの主な原因であったピロリ菌の検査や除菌治療が普及し、ピロリ菌に感染していない方が増えました。それに伴い、このような新しいタイプの胃がんが注目されるようになっています。
まずは、この病気がどのようなものなのか、3つの主な特徴を一緒に見ていきましょう。正しい知識を持つことが、不安を和らげる第一歩になります。
ラズベリーのような見た目の発赤と好発部位
ラズベリー様胃がんの最も大きな特徴は、その名前が示す通り、内視鏡で見たときの様子にあります。まるで果物のラズベリーのように、赤くて表面がブツブツ、ザラザラとした小さな盛り上がりに見えます。
専門的には「発赤調(ほっせきちょう)で表面が顆粒状(かりゅうじゅう)の小隆起(しょうりゅうき)」と表現されます。この腫瘍の詳しい特徴を、以下の表にまとめました。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 見た目 | 赤みを帯びていて、表面がザラザラした小さな盛り上がりです。特殊な光(NBI)で拡大して観察すると、脳のシワのような模様が見えることがあります。 |
| 大きさ | 非常に小さく、発見されるもののほとんどが5mm以下です。 |
| できやすい場所 | 胃の上部、食道とのつなぎ目に近い「穹窿部(きゅうりゅうぶ)」や、胃の本体である「胃体部(いたいぶ)」にできやすい傾向があります。 |
特に、腫瘍ができやすい胃の上部は、通常の胃カメラ検査ではヒダに隠れてしまい、少し観察しにくい場所です。大きさも非常に小さいため、見逃さないためには、経験豊富な医師による注意深い観察と高い技術が求められます。
自覚症状はほとんどなくピロリ菌のいない胃に発生
ラズベリー様胃がんは、初期の段階では自覚できる症状がほとんどないことも大きな特徴です。胃の痛み、胸やけ、食欲不振、もたれといった、いわゆる胃の不調を感じることはまずありません。
これは、がんが粘膜の非常に浅い部分にとどまっているため、痛みを感じる神経などを刺激しないためです。そのため、ご自身で不調に気づいて病院を受診するというよりは、症状のない方が受けた健康診断や人間ドックの胃カメラ検査で、偶然発見されるケースがほとんどです。
また、発生する「胃の環境」にも、一般的な胃がんとは決定的な違いがあります。
- 一般的な胃がん主な原因はピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の長期間の感染です。ピロリ菌によって胃粘膜が荒らされ、薄くやせてしまった状態(萎縮性胃炎)から発生することが多いとされています。
- ラズベリー様胃がんピロリ菌に感染していない、または除菌治療を終えた後の、萎縮のないきれいな胃粘膜に発生します。
「ピロリ菌を除菌したから、もう胃がんの心配はない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ピロリ菌がいない胃からも、ラズベリー様胃がんのような新しいタイプの胃がんが発生することがわかってきています。定期的な胃カメラ検査が重要であることに変わりはありません。
悪性度は低く進行は緩やかだが胃がんの一種
「がん」という言葉を聞くと、すぐに進行して転移してしまうのではないかと、とても心配になることと思います。しかし、ラズベリー様胃がんは、一般的な胃がんと比較すると、性質がおとなしく、進行が非常に緩やかであることが分かっています。
この腫瘍の性質を正しく理解し、過度に心配しすぎないようにしましょう。
- 悪性度と進行悪性度は低いと考えられています。進行も非常にゆっくりで、血液やリンパ液の流れに乗って他の臓器に転移(リンパ節転移や遠隔転移)することは、現在のところ報告されておらず、極めてまれだと考えられています。
- 医学的な分類世界保健機関(WHO)の分類では、「腺腫(せんしゅ)」という、良性のポリープに近いグループに位置づけられています。しかし、日本では、将来的にがんとしての性質を持つ可能性があることから、「がん(専門的には上皮内がん)」として扱い、慎重に対応するのが一般的です。
- がんの深さ組織を顕微鏡で詳しく調べると、がん細胞が粘膜の最も表面の層(上皮)にとどまっていることがわかります。これは、がん細胞が粘膜の奥深くに染み込むように広がっていく「浸潤(しんじゅん)」を起こしていない状態です。
このように、ラズベリー様胃がんは過度に心配する必要はありませんが、胃がんの一種であることには変わりありません。放置せずに、専門医のもとで適切な経過観察や治療を受けることが大切です。
ラズベリー様胃がんの診断に不可欠な2つの検査
健康診断で「ラズベリー様胃がんの疑い」と告げられると、「本当にがんなの?」「これからどうなるの?」と、大きな不安に襲われることでしょう。
しかし、疑いがあるからといって、すぐにがんと決まったわけではありません。大切なのは、焦らずに精密な検査を受け、病気の正体を正確に突き止めることです。ここでは、診断を確定させるために欠かせない2つの検査を、わかりやすく解説します。
特殊な光で観察する胃カメラ(NBI拡大内視鏡)
ラズベリー様胃がんの診断で、最も中心的な役割を果たすのが胃カメラ検査です。特に「NBI」という特殊な光と、病変を大きく映す拡大機能がとても役立ちます。
NBIとは、がんが栄養をもらうために作る、異常な血管を見つけやすくする技術です。特定の波長の青い光を胃の粘膜に当てることで、粘膜表面の細かい血管や模様が、はっきりと浮かび上がって見えるようになります。
このNBIを使い、さらにカメラでグッと拡大して観察すると、ラズベリー様胃がんに特徴的な、以下のようなサインを捉えることができます。
- 表面の模様脳のシワのような、あるいはラズベリーの粒のような、独特のザラザラした模様が見えます。専門的には「乳頭状(にゅうとうじょう)・脳回様(のうかいよう)構造」と呼びます。
- 血管の様子正常な血管とは違う、太く拡張した異常な血管が観察されます。
- 模様の隙間ザラザラした模様と模様の間の隙間が、広く見えるのも特徴の一つです。
通常の光では見逃してしまうような、ごく初期の小さな変化も見つけ出すことができます。これらの特徴を詳しく観察し、病気の正体に迫るのが第一歩です。
確定診断のために組織を採取する生検
胃カメラでラズベリー様胃がんが強く疑われる部分が見つかった場合、次に行うのが「生検(せいけん)」という検査です。これは、病気の最終的な答えを出すための、とても重要なステップになります。
生検では、胃カメラの先端から出した小さな器具で、疑わしい組織を米粒ほどの大きさで数カ所つまみ取ります。痛みはほとんど感じませんので、ご安心ください。
採取した組織は、顕微鏡を使って専門家が詳しく調べる「病理組織検査」に回されます。この検査で、細胞の顔つきを細かく観察し、がん細胞がいるかどうかを最終的に判断します。これを「確定診断」と呼びます。
ラズベリー様胃がんは、組織を調べると胃の粘膜の表面にとどまっている、おとなしい性質のがん細胞であることがほとんどです。世界保健機関(WHO)の分類では良性の「腺腫(せんしゅ)」に近い扱いですが、日本では将来がんになる可能性を考え、慎重を期して「がん」として診断するのが一般的です。
似た見た目の「過形成性ポリープ」との鑑別点
ラズベリー様胃がんには、見た目がそっくりな「過形成性(かけいせいせい)ポリープ」という良性のポリープがあります。こちらはがんではないため、治療の方針が全く異なります。
そのため、この2つを正確に見分けること(鑑別)が、非常に重要になります。経験豊富な医師がNBI拡大内視鏡で詳しく観察すれば、多くの場合、生検をしなくても見た目の違いで見分けることが可能です。
| 鑑別ポイント | ラズベリー様胃がん | 過形成性ポリープ |
|---|---|---|
| 色 | 発色が強く、濃い赤色に見えます。 | 明るい赤色をしています。 |
| 表面の模様 | 顆粒状でラズベリーのような模様がはっきりしています。 | 比較的つるっとしています。 |
| 境界線 | 周りの正常な粘膜との境目がくっきりしています。 | 境目が少しぼやけていることがあります。 |
| 白い縁取り | 模様の周りに、白い線が見られることがあります。 | 見られないことがほとんどです。 |
これらの細かな違いを見極めるには、高性能な内視鏡の設備と、それを熟知した医師の技術の両方が不可欠です。正確な診断が、適切な治療への第一歩となります。
ラズベリー様胃がんの治療法と治療後の注意点
「ラズベリー様胃がん」と診断されると、「がん」という言葉の響きに、大きな不安を感じてしまうかもしれません。
しかし、このがんは早い段階で見つかることがほとんどです。そのため、体に大きな負担をかけることなく、完治を目指せる可能性が非常に高い病気です。
ここでは、具体的な治療法や治療後の生活について詳しく解説します。治療の全体像を知ることで、少しでも安心して一歩を踏み出していただければと思います。
体への負担が少ない内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
ラズベリー様胃がんの治療は、お腹を切る手術ではなく、胃カメラを使った治療が中心となります。
なぜなら、このがんは胃の壁の表面にある「粘膜」という薄い層にだけ、とどまっているからです。血管やリンパ管が集まる深い層まで達していないため、がん細胞が血液の流れに乗って他の場所に飛んでいく「転移」の心配は、まずありません。
そのため、がんがある部分だけを正確に取り除く、内視鏡治療で十分に対応できます。その代表的な治療法が「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」です。
- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)とは? 口から入れた胃カメラの先から、細い電気メスを出します。そして、がんのある部分の粘膜だけを、まるでリンゴの皮をむくように、薄くきれいに剥ぎ取って取り除く治療法です。
このESDという治療法には、患者さんにとって多くの良い点があります。
| ESDのメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 体への負担が少ない | お腹に傷がつかないため、手術後の痛みが少なく、体力の回復も非常に早いです。 |
| 胃の働きを保てる | 胃を切り取ることがないため、治療前とほとんど変わらない食生活を送ることができます。 |
| 入院期間が短い | 患者さんの状態にもよりますが、通常、入院は1週間程度で済みます。 |
もちろん、どんな治療にもリスクは伴います。ESDでは、治療後に出血したり、胃に小さな穴が開いたり(穿孔)することがあります。しかし、その多くは内視鏡を使った処置で対応可能ですので、過度な心配は必要ありません。
実際に治療が必要かどうか、どの方法が最適かは、がんの大きさやできた場所などを総合的に評価し、医師が慎重に判断します。
治療後の予後と再発させないための定期検診
内視鏡治療でがんを完全に取り除くことができれば、ラズベリー様胃がんの治療後の見通し(予後)は非常に良好です。
治療した場所から再びがんが発生したり、他の臓器に転移したりする心配はほとんどありません。これは、このがんが粘膜の表面にとどまる、おとなしい性質を持っているからです。
ただし、「治療が終わればすべて安心」というわけではありません。ラズベリー様胃がんが一度できたということは、胃の他の場所に、また同じような病気ができる可能性があるというサインでもあります。
そのため、治療が終わった後も、定期的に胃カメラ検査を受けることが非常に大切になります。
定期検診の主な目的
- 治療した場所のチェック 治療した部分が、やけどの跡のようにきれいに治っているかを確認します。
- 新しい病変の早期発見 胃の他の場所に、新しいがんやポリープができていないかを隅々までチェックします。
- 負担の少ない治療のため 万が一、再発や新しい病変が見つかっても、ごく初期の段階で発見できれば、再び体への負担が少ない内視鏡治療で対応できます。
検査を受ける頻度は、患者さんの胃の状態によって異なります。一般的には、治療後数年間は年に1回程度の胃カメラ検査が勧められます。医師の指示に従って検診を受け、ご自身の胃の健康を長く見守っていきましょう。
大分市で相談できる「わだ内科・胃と腸クリニック」の胃カメラ検査
「健康診断で異常を指摘された」「もしかしたらラズベリー様胃がんかもしれない」など、胃に関するお悩みや心配事がございましたら、大分市津守にある「わだ内科・胃と腸クリニック」へご相談ください。
当クリニックでは、消化器内視鏡の専門医が、正確な診断から治療方針のご相談まで、お一人おひとりに寄り添いながら丁寧に対応いたします。ラズベリー様胃がんの診断には、質の高い胃カメラ検査が何よりも重要です。
当クリニックでは、患者さんが安心して検査を受けられるよう、以下の体制を整えています。
- 高性能な内視鏡システム 特殊な光を備えた最新の内視鏡を導入しています。ラズベリー様胃がん特有の、脳のシワのような表面構造を詳しく観察し、小さな病変も見逃しません。
- 苦痛を和らげる検査 ご希望に応じて鎮静剤を使い、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けていただけます。嘔吐反射が強い方や、検査に強い不安を感じる方もご安心ください。
- その場での組織検査(生検) 検査中に疑わしい部分が見つかった場合は、その場で組織の一部を採取できます。この組織を詳しく調べることで、がんかどうかを最終的に確定させることが可能です。
検査や治療について、ご不明な点や不安なことがあれば、どんな些細なことでもお尋ねください。皆様の健康を守るパートナーとして、最適な医療を提供できるよう努めてまいります。
まとめ
今回は、ラズベリー様胃がんの特徴から治療法までを詳しく解説しました。
この病気は、ピロリ菌のいないきれいな胃にできる、比較的新しいタイプの胃がんです。「がん」という名前に不安を感じるかもしれませんが、進行が非常に緩やかで、転移の心配もほとんどないおとなしい性質を持っています。
大切なのは、自覚症状がほとんどないため、定期的な胃カメラ検査で早期に発見することです。早期に見つかれば、体への負担が少ない内視鏡治療で完治を目指せます。
健康診断で指摘されたり、ご自身の胃の状態が気になったりした際は、一人で抱え込まず、消化器内科の専門医に相談してみましょう。
参考文献
- 柴垣広太郎, 高橋佑典, 石原俊治. 「ラズベリー様」腺窩上皮型胃腫瘍の臨床・病理学的特徴.