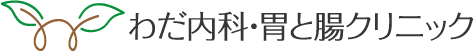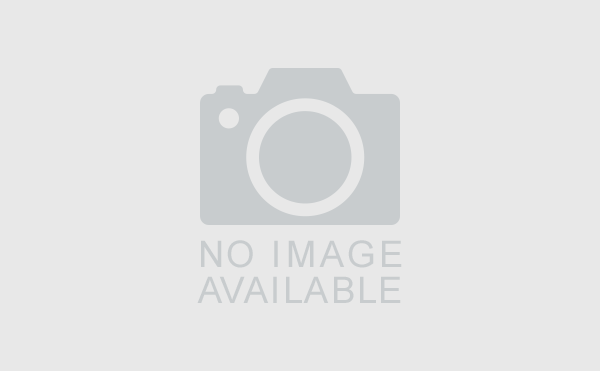帯状疱疹発症後、どのくらい間隔をあけたらワクチン接種は可能?
大分県大分市のわだ内科・胃と腸クリニック院長の和田蔵人(わだ くらと)です。「二度とあんな思いはしたくない」―。帯状疱疹のつらい痛みを経験された方なら、誰もがそう強く願っていることでしょう。しかし残念ながら、帯状疱疹は一度治っても、加齢やストレスで免疫力が下がると再発する可能性がある病気です。
その再発リスクを大きく減らす有効な手段が「帯状疱疹ワクチン」です。ですが、一度かかった後だからこそ、「いつから接種できるの?」「まだ痛みが残っていても大丈夫?」といった、いざ接種を考えた時に浮かぶ疑問も多いのではないでしょうか。
この記事では、帯状疱疹にかかった後のワクチン接種について、専門家が推奨する具体的な接種間隔や、2種類のワクチンの違い、治療中の注意点などを詳しく解説します。あなたの疑問を解消し、未来のつらい痛みからご自身を守るための、最適な一歩を見つけましょう。
帯状疱疹ワクチンで再発を防ぐための基礎知識3選
帯状疱疹のつらい痛みを一度経験されると、「二度とあんな思いはしたくない」と心から感じているのではないでしょうか。
帯状疱疹は、一度治っても残念ながら再発する可能性がある病気です。 しかし、ワクチンを接種することで、その再発リスクを大きく減らせます。 ここでは、帯状疱疹の再発を防ぐために知っておきたい3つの大切な知識を、わかりやすく解説します。
なぜ一度かかっても再発する?潜伏するウイルスと免疫力の関係
「どうして一度かかったのに、また帯状疱疹になるの?」 この疑問の答えは、原因ウイルスが体に隠れ続ける性質にあります。
帯状疱疹の原因は「水痘・帯状疱疹ウイルス」という名前です。 これは、多くの方が子どもの頃にかかる「水ぼうそう」と同じウイルスです。 水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体の中から完全には消えません。
体の奥深くにある神経の根元(神経節)に、何十年もの間、静かに隠れ続けます。 近年の研究では、体の感覚を伝える神経だけでなく、内臓の働きを調整する交感神経や、お腹の腸の神経にも、このウイルスが潜んでいる可能性がわかってきました。
普段は、体の「免疫」というガードマンがウイルスをしっかりと見張っているため、何も症状は出ません。 しかし、加齢やストレスなどで免疫力が下がると、潜んでいたウイルスが目を覚まして再び活発になり、神経を伝って皮膚に現れます。 これが帯状疱疹であり、いわば「体の中に潜んでいたウイルスによる再発」なのです。
免疫力が下がる主なきっかけ
- 加齢
- 特に50歳を過ぎると免疫力が低下しやすく、発症リスクが高まります。
- 過労やストレス
- 心と体の疲れは、免疫の働きを弱める大きな原因です。
- 病気
- 糖尿病やがん、HIV感染症などの治療を受けている方。
- 薬の影響
- ステロイド薬や免疫抑制薬など、免疫の働きを抑える薬を使っている場合。
帯状疱疹は、新たに外からうつる病気ではありません。 自分自身の体内にいるウイルスが原因だからこそ、ワクチンが重要になります。 ワクチンで免疫力を高め、ウイルスの再活動を力強く抑え込むことが、再発予防につながるのです。
2種類のワクチンの違い:不活化(シングリックス)と生ワクチン(ビケン)
帯状疱疹の再発予防に使われるワクチンには、2つの種類があります。 「不活化ワクチン」と「生ワクチン」です。 それぞれの特徴をよく理解し、ご自身の状況に合わせて選ぶことがとても大切です。
| 項目 | 不活化ワクチン(シングリックス) | 生ワクチン(ビケン) |
|---|---|---|
| ワクチンの仕組み | ウイルスの一部だけを使用し、体内で増えない | 毒性を弱めた生きたウイルスを使用 |
| 接種対象 | 50歳以上の方 | 50歳以上の方 |
| 接種回数 | 筋肉注射を2回(2ヶ月あけて) | 皮下注射を1回 |
| 発症予防効果 | 非常に高い(50歳以上で97%以上) | 約50~60% |
| 効果の持続 | 10年程度と長い | 5年程度 |
| 注意点 | 免疫力が低い方にも接種可能 | 免疫力が著しく低い方は接種できない |
不活化ワクチン(シングリックス)
ウイルスの表面にあるタンパク質の一部だけを取り出して作られています。 そのため、ワクチン成分が体の中でウイルスとして増えることはありません。 免疫の働きを強力に後押しする「アジュバント」という助っ人が入っており、非常に高い予防効果を発揮するのが大きな特徴です。
その効果は、50歳以上の方で97%以上と報告されています。 効果の持続期間も10年程度と長く、免疫機能が低下している方でも接種できるのが強みです。
生ワクチン(ビケン)
水ぼうそうの予防にも使われる、生きたウイルスを用いたワクチンです。 ただし、ウイルスの毒性は、病気を起こさないレベルまで十分に弱められています。 研究によると、特に皮膚でウイルスが増える力が抑えられていることがわかっています。
1回の接種で済む手軽さが利点です。 しかし、発症予防効果や効果の持続期間はシングリックスに比べると限定的です。 また、生きたウイルスを使っているため、免疫機能が著しく低下している方や妊娠中の方は接種できません。
どちらのワクチンを選ぶかは、予防効果や費用、ご自身の健康状態などを総合的に考えて、主治医としっかり相談することが重要です。
帯状疱疹後神経痛(PHN)などつらい合併症の予防効果
帯状疱疹の本当の怖さは、皮膚の発疹が治った後も長く続く、つらい合併症にあると言えます。 その代表が「帯状疱疹後神経痛(PHN)」です。
PHNは、ウイルスによって神経が深く傷つけられてしまうことで起こります。 皮膚の見た目はすっかりきれいになっても、激しい痛みが数ヶ月から数年にわたって続くことがあります。 「焼けるような痛み」「電気が走る感覚」「締め付けられる痛み」などと表現され、日常生活を送るのも困難になるほどつらい症状です。
さらに、帯状疱疹の合併症は痛みだけではありません。 最近の研究では、ウイルスが神経を伝わって再活性化することで、全身にさまざまな影響を及ぼす可能性が指摘されています。
注意したい帯状疱疹の合併症
- 血管のトラブル
- ウイルスが血管に影響を及ぼし、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めることがあります。
- 顔面神経麻痺
- 顔の神経でウイルスが暴れ、顔の筋肉が動かしにくくなる「ラムゼイ・ハント症候群」。
- 耳の症状
- 耳の神経に影響が及ぶと、難聴やめまいが起こることがあります。
- お腹の不調
- 腸の神経でウイルスが再活性化し、便秘などの腸の動きの異常につながることも報告されています。
帯状疱疹ワクチンは、こうしたつらい合併症を防ぐ上で非常に有効です。
- 帯状疱疹の発症そのものを防ぐ
- ワクチンの最大の目的です。発症しなければ、当然ながら合併症の心配もありません。
- PHNの発症リスクを大幅に下げる
- 特に不活化ワクチン(シングリックス)は、PHNの発症を約90%減らすという高い予防効果が報告されています。
- 万が一発症しても、症状を軽くする効果が期待できる
- ワクチンを接種していれば、もし帯状疱疹にかかってしまっても、症状が軽く済む傾向にあります。
ワクチン接種は、将来のつらい痛みや生活の質の低下を防ぐための、とても大切な「未来への自己投資」と言えるでしょう。 生涯を通じたワクチン接種が、ウイルス関連疾患の負担を減らす効果的な戦略となりうるという考え方も提唱されています。 ご自身の健康な未来を守るために、ぜひワクチン接種をご検討ください。
帯状疱疹にかかった後のワクチン接種に関する4つの疑問
帯状疱疹のつらい症状を乗り越えられた後、「もう二度と経験したくない」と強く願うのは当然のことです。
帯状疱疹は再発の可能性がある病気だからこそ、ワクチンによる予防がとても大切になります。 しかし、一度かかった後となると、様々な疑問が浮かびますよね。
- 「ワクチンは、いつから打てるのだろう?」
- 「まだ痛みが残っているけど、大丈夫かな?」
こうした疑問は、ご自身の体を大切に思うからこそ生まれるものです。 ここでは、皆さまが安心してワクチン接種を検討できるよう、帯状疱疹にかかった後のワクチン接種に関する疑問に、一つひとつ丁寧にお答えします。
発症から回復後、推奨される具体的な接種間隔
帯状疱疹の症状が落ち着いたからといって、すぐにワクチンを接種することは通常ありません。 体がウイルスとの戦いから回復し、ワクチンの効果を最大限に引き出す準備ができるまで、少しお休み期間を設けることが大切です。
では、具体的にどのくらいの間隔をあければ良いのでしょうか。 世界中で統一された明確な決まりはありませんが、多くの専門家は、皮膚の発疹などがすっかり良くなってから、2ヶ月から半年ほど間隔をあけることを推奨しています。
これは、帯状疱疹を発症した直後の体の中では、ウイルスと戦うための免疫が自然にとても活発になっているためです。 この時期にワクチンを接種しても、本来期待される効果が十分に得られない可能性があるのです。
特に、もともと免疫機能が低下しやすいご病気をお持ちの方やご高齢の方は注意が必要です。 アジア太平洋地域で行われた研究でも、自己免疫疾患などを持つ方は、一般の方に比べて帯状疱疹を再発するリスクが高いことが報告されています。
このような方々にとって、適切なタイミングでのワクチン接種は、再発を防ぐための非常に重要な一手となります。 ご自身の回復状態に合わせて最適な時期を見極めるため、自己判断はせず、必ず医師に相談しましょう。
なぜ発症後すぐにワクチンを接種できないのか
「再発が怖いから、一日でも早くワクチンを打ちたい」 そのお気持ちは、痛みを経験された方なら誰でも感じることだと思います。
しかし、発症後すぐに接種しないのには、医学的に大切な理由が2つあります。 焦らずに適切な時期を待つことが、ワクチンの効果をしっかり得るための近道なのです。
- 体の免疫システムが活発に働いているから 帯状疱疹を発症すると、体は原因ウイルスを追い出すために免疫システムを総動員します。 この働きによって、ウイルスに対する免疫力が一時的にとても高まった状態になります。 このタイミングでワクチンを接種しても、ワクチンが作り出す免疫の効果が、体が自然に作った免疫に隠れてしまい、十分な予防効果を発揮できない可能性があるのです。
- 体の回復を最優先するため 帯状疱疹は、皮膚の炎症だけでなく神経にもダメージを与え、体にとって大きな負担となります。 体はまず、このダメージを治すことに全力を注がなければなりません。 ワクチン接種は、体に軽い刺激を与えて免疫をつくる行為です。 体が弱っている時に接種すると、回復が遅れたり、発熱などの副反応が強く出たりする心配があります。
まずは体の声に耳を傾け、しっかりと回復させる時間をとることが、結果的に未来の健康を守ることにつながります。
抗ウイルス薬での治療中や痛みが残っている場合の接種可否
治療中や痛みが続く中でのワクチン接種について、心配される方も多いでしょう。 これは状況によって判断が異なりますので、一つずつ解説します。
抗ウイルス薬での治療中の場合
アシクロビルやバラシクロビルといった抗ウイルス薬を飲んでいる最中のワクチン接種は、原則として行いません。 まずは薬の力でウイルスの活動をしっかりと抑え、症状を改善させる治療に専念することが最優先です。 治療が完了し、体の状態が落ち着いてから接種を計画しましょう。
痛みが残っている場合(帯状疱疹後神経痛)
皮膚の症状が治った後も、ピリピリ、ズキズキとした痛みが続く「帯状疱疹後神経痛(PHN)」に悩まされることがあります。 このPHNによる痛みが残っている状態でも、急性期(症状が最も激しい時期)を過ぎていればワクチン接種は可能です。
むしろ、ワクチンは帯状疱疹の再発を防ぐだけでなく、このつらいPHNの発症リスクを下げる効果も期待されています。 痛みの治療と再発予防は、どちらも生活の質を守るために非常に重要です。
最近では、帯状疱疹に関連するつらい痛みを和らげるための治療法も進歩しています。
痛みの治療をきちんと行いながら、再発予防のためのワクチン接種を医師と一緒に考えていきましょう。
ワクチンの種類によって推奨される接種時期は違うのか
現在、日本で接種できる帯状疱疹ワクチンには2種類あります。 帯状疱疹にかかった後の接種タイミングは、どちらのワクチンも「急性期を過ぎて回復してから」という点で共通しています。 しかし、それぞれの特徴は大きく異なるため、ご自身に合った選択が重要です。
接種時期そのものに大きな違いはありませんが、特に注意したいのは「誰が接種できるか」という点です。 持病(自己免疫疾患など)やその治療(免疫抑制薬の使用など)によって免疫機能が低下している方は、帯状疱疹の再発リスクが高いことが研究で示唆されています。
このような方は、生きたウイルスを使用する生ワクチンを接種できません。 そのため、ウイルスの成分だけを使った不活化ワクチン(シングリックス)が、唯一かつ非常に重要な選択肢となります。 ご自身の健康状態やライフスタイルに合わせて、どちらのワクチンが最適か、医師としっかり相談して決めましょう。
他のワクチン(インフルエンザなど)との同時接種について
季節によっては、インフルエンザワクチンや、ご高齢の方であれば肺炎球菌ワクチンなど、他のワクチン接種も考える必要があります。 帯状疱疹ワクチンと他のワクチンを一緒に打てるかどうかは、ワクチンの種類によってルールが異なります。
- 不活化ワクチン(シングリックス)の場合
- インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなど、他の「不活化ワクチン」とは、医師が必要と認めれば同じ日に接種できます。
- ただし、新型コロナワクチンとの同時接種はできず、互いに13日以上の間隔をあける必要があります。
- 生ワクチン(ビケン)の場合
- 生ワクチンを接種した場合は、次に別の種類のワクチンを接種するまでに、原則として27日以上(4週間)の間隔をあける必要があります。
どのワクチンをいつ接種するかは、健康を守るための大切な計画です。 近年では、水痘や帯状疱疹だけでなく、様々な感染症に対して生涯にわたるワクチン接種計画を立てることが、健康寿命を延ばす上で効果的だという考え方が広まっています。
接種を希望するワクチンを医師に伝え、あなたにとって最適な接種スケジュールを一緒に計画していきましょう。
まとめ
今回は、帯状疱疹にかかった後のワクチン接種のタイミングや注意点について詳しく解説しました。 一度つらい痛みを経験すると、再発への不安は大きいですよね。帯状疱疹ワクチンは、その再発を防ぐための非常に有効な手段です。
接種の目安は、皮膚の症状がすっかり回復してから2ヶ月から半年ほど経った頃。 焦らず、まずは体の回復を優先することが、ワクチンの効果を最大限に引き出す鍵となります。
痛みが残っていても接種は可能ですし、効果の高いワクチンも登場しています。 ご自身の体の状態や持病に合わせて最適なワクチンや時期を選ぶことが何よりも大切です。 再発の不安を解消し、未来の健康を守るために、まずはかかりつけの医師に気軽に相談してみてくださいね。
参考文献
Casabona G, Bonanni P, Gabutti G, Vetter V, Duchenne M and Parikh R. “Breaking the cycle: considerations for a life-course vaccination strategy against varicella-zoster virus.” Expert review of vaccines 24, no. 1 (2025): 556-569.
Ding XT, Huang JZ, Shen QS, Wang RY and Kan HM. “Effects of pulsed radiofrequency combined with ozone on zoster-associated pain: a systematic review and meta-analysis.” Medical gas research 16, no. 1 (2026): 76-81.
Gershon AA and Gershon MD. “A fresh look at varicella vaccination.” Human vaccines & immunotherapeutics 21, no. 1 (2025): 2488099.
Tommasi C, Drousioti A and Breuer J. “The live attenuated varicella-zoster virus vaccine vOka: Molecular and cellular biology of its skin attenuation.” Human vaccines & immunotherapeutics 21, no. 1 (2025): 2482286.
Chen J, Ho CY, Tu YK, Lin YC, Hsia Y, Lin YC and Shantakumar S. “A systematic review and meta-analysis of herpes zoster risk in adults with immunocompromised conditions and autoimmune diseases in Asia-Pacific.” Human vaccines & immunotherapeutics 21, no. 1 (2025): 2496048.