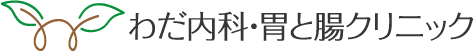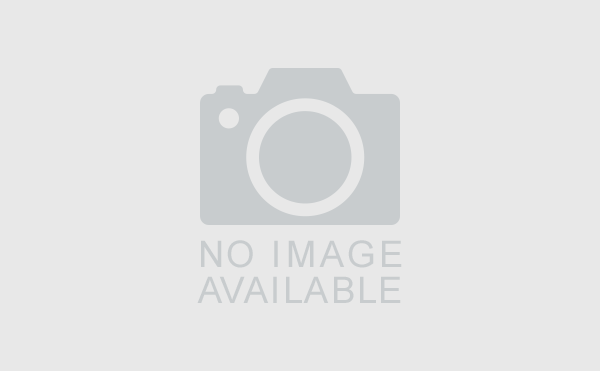暑い夏には清暑益気湯
大分県大分市のわだ内科・胃と腸クリニック院長の和田蔵人(わだ くらと)です。「なんだか体がだるい」「食欲が全然わかない」。夏の厳しい暑さは、私たちの心と体にさまざまな不調をもたらします。そんな夏のつらい悩みのために、古くから用いられてきたのが漢方薬「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」です。
その名の通り、暑さによる不調を取り除き(清暑)、生命活動のエネルギーである「気」を補う(益気)この漢方薬。しかし、その力は夏バテや熱中症予防だけだと思っていませんか?
実は、夏特有の下痢や食欲不振はもちろん、季節を問わない長引く咳や息切れといった意外な症状にも応用される可能性が注目されています。この記事では、清暑益気湯に期待できる5つの効果から正しい使い方まで、専門医が詳しく解説します。
清暑益気湯とは?夏バテから喘息まで期待できる5つの効果
「なんだか体がだるい」「食欲が全然わかない」。 夏の厳しい暑さは、私たちの心と体にさまざまな不調をもたらします。
そんな夏のつらい悩みに寄り添うため、古くから用いられてきた漢方薬があります。 それが「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」です。
この名前には、とても分かりやすい意味が込められています。
- 清暑(せいしょ)
- 暑さによる体への悪い影響を取り除き、体をクールダウンさせる
- 益気(えっき)
- 生命活動のエネルギー源である「気」を補い、元気をプラスする
文字通り、夏の暑さで消耗した体に元気とうるおいを取り戻すための漢方薬です。 主に夏バテや暑気あたりに使われますが、その力は夏だけに留まりません。
この記事では、清暑益気湯に期待できる5つの効果について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
汗のかきすぎによる倦怠感や食欲不振を改善する(夏バテ・熱中症予防)
夏の暑い日に汗をかくのは、体温を調節するための大切な体の仕組みです。 しかし、汗をかきすぎてしまうと、体にとって重要なものまで失われてしまいます。
漢方では、汗とともに2つのものが体から出ていくと考えます。
- 気(き)
- 体を動かすための「元気のもと」となるエネルギー
- 津液(しんえき)
- 体をうるおし、正常に機能させるための「きれいな水分」
これらが不足すると、夏バテ特有のつらい症状が現れやすくなります。
- 体が鉛のように重く、だるい(倦怠感)
- 食欲がまったくわかない
- 口やのどがカラカラに渇く
- 体に熱がこもって、ほてる感じがする
- おしっこの量が減る
清暑益気湯は、汗で失われた「気」と「津液」を効率よく補ってくれる漢方薬です。 体にエネルギーをチャージし、うるおいを取り戻すことで、夏バテの症状を和らげます。
また、熱中症になってしまった後の回復を早めたいときにも役立ちます。 猛暑日に屋外で作業する方や、スポーツをする方が熱中症を予防する目的で服用することもあります。
胃腸の働きを整え下痢や軟便を止める
「夏になると、決まってお腹の調子が悪くなる」。 「冷たいものを飲むと、すぐにお腹を壊してしまう」。 このような経験をお持ちの方は、少なくないのではないでしょうか。
暑い季節は、アイスやかき氷、冷たいジュースなどをつい摂りすぎてしまいがちです。 また、暑さそのものが体へのストレスとなり、胃腸の働きを弱らせることもあります。
胃腸の機能が低下すると、食べたものをうまく消化・吸収できなくなります。 その結果、食欲不振や下痢、軟便といった症状につながってしまうのです。
清暑益気湯には、弱った胃腸の働きを助け、元気にする生薬が含まれています。
- 余分な湿気を取り除く
- 胃腸にたまった不要な水分(湿邪)を追い出し、働きやすい環境を整えます。
- 消化機能を高める
- 弱った胃腸を元気づけ、食べ物をエネルギーに変える力をサポートします。
- 下痢を抑える
- 含まれている五味子(ごみし)という生薬の働きで、腸から水分が漏れ出るのを防ぎます。
このように、清暑益気湯は胃腸の機能を多角的に整えることで、夏特有の下痢や食欲不振を改善に導きます。 夏になると必ずお腹の調子を崩すという方は、この漢方薬が体質に合っているかもしれません。
長引く咳や息切れ(気管支喘息)への応用
清暑益気湯は「夏バテの薬」というイメージが強いかもしれません。 しかし、その効果は夏だけに限定されず、呼吸器の症状にも応用されています。
近年、長引く咳や息切れ、特に気管支喘息の治療に使える可能性が注目されています。 ある研究では、季節を問わず、なかなか改善しない気管支喘息の患者さんに清暑益気湯を処方したところ、良い結果が得られたと報告されました。
この研究によると、特に次のような症状を持つ喘息の方に効果が見られやすかったとされています。
- のどに何かが張り付いたような不快感やイガイガ感
- 胸のあたりがドキドキする(動悸)
- じっとしていても汗をかきやすい
これらの症状を持つ患者さんが清暑益気湯を服用したところ、喘息発作の回数が大幅に減ったり、呼吸が楽になったりといった改善が認められたのです。 中には、吸入ステロイド薬の量を減らせた方もいました。
これは、清暑益気湯が持つ「気(エネルギー)」と「津液(うるおい)」を補う力が、空気の通り道である気道の状態を整え、過敏になっているのを和らげるためと考えられます。
夏バテと喘息は一見すると無関係に思えるかもしれません。 しかし漢方では、体の根本にある「消耗」という同じ原因にアプローチすることで、異なる症状を同時に改善に導くことができるのです。 この研究は、清暑益気湯が特定のタイプの気管支喘息に対し、季節を問わず長期的な管理薬として使える可能性を示しています。
体力と気力を補う生薬の組み合わせと働き
清暑益気湯が夏バテから喘息まで、幅広い症状に対応できるのには理由があります。 それは、さまざまな働きを持つ生薬(しょうやく)が、絶妙なバランスで配合されているからです。 それぞれの生薬が専門チームのように協力し合い、一つの漢方薬として大きな力を発揮します。
| 役割 | 代表的な生薬 | 主な働き(分かりやすく言うと…) |
|---|---|---|
| エネルギーを補う担当 | 人参(にんじん)、黄耆(おうぎ) | 「元気のもと」を体にチャージし、疲れやだるさを吹き飛ばします。 |
| うるおい補給担当 | 麦門冬(ばくもんどう)、五味子(ごみし) | 汗で失われた体の水分を補給し、のどの渇きや乾いた咳を鎮めます。 |
| お腹の調子を整える担当 | 蒼朮(そうじゅつ)、陳皮(ちんぴ) | 弱った胃腸の働きを助け、食欲不振や下痢を改善します。 |
| 熱さまし担当 | 黄柏(おうばく) | 体にこもった余分な熱を冷まし、ほてりやのぼせを和らげます。 |
| まとめ役のリーダー | 甘草(かんぞう) | チーム全体の働きを調整し、薬の効果をスムーズにします。 |
このように、清暑益気湯は複数の働きを同時に行います。 単に体力をつけるだけでなく、熱を冷まし、うるおいを補い、胃腸を整える。 この総合力こそが、夏の複雑な不調を根本から改善に導く鍵なのです。
似ている漢方薬「補中益気湯」との使い分け
疲れや体力の低下に使われる漢方薬に、清暑益気湯とよく似た名前の薬があります。 それは「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」です。
どちらも「気」を補う代表的な漢方薬ですが、得意なことや使われる場面が異なります。 この2つの使い分けは、漢方治療において非常に重要です。
| 項目 | 清暑益気湯(せいしょえっきとう) | 補中益気湯(ほちゅうえっきとう) |
|---|---|---|
| 得意な季節 | 夏 | 通年(特に季節の変わり目など) |
| 主な原因 | 暑さ、湿気、汗のかきすぎ | 慢性的な疲れ、胃腸の弱さ、ストレス |
| 特徴的な症状 | 強いのどの渇き、多汗、体の熱っぽさ、下痢 | 食後の強い眠気、手足のだるさ、声に力がない |
| 得意ワザ | 体の熱を冷まし、うるおいを補う | 弱った胃腸の働きを持ち上げ、気力を補う |
ポイントを簡単にまとめると、以下のようになります。
- 清暑益気湯が合う人
- 「夏の暑さにやられて、汗をだらだらとかき、体は熱っぽく、のどがカラカラでぐったりしている」タイプ
- 補中益気湯が合う人
- 「季節に関係なく、もともと胃腸が弱くて疲れやすく、気力がわかない」タイプ
ご自身の症状がどちらに近いか、考えてみるのも良いでしょう。 しかし、最適な漢方薬を選ぶには、専門的な知識と診察が不可欠です。 自己判断で選ぶのではなく、ぜひ一度クリニックでご相談ください。
清暑益気湯の正しい服用法と注意すべき4つのポイント
清暑益気湯は、夏のつらい症状に効果が期待できる漢方薬です。 しかし、どんなお薬も正しく使ってこそ、その力が十分に発揮されます。
飲み方や飲む期間を誤ると、せっかくの効果が十分に得られなかったり、思わぬ不調につながったりすることもあります。 安心して服用いただくために、知っておいていただきたい大切なポイントが4つあります。
ここでは、お薬を飲むタイミングや期間の目安、そして副作用や注意が必要なケースについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。 ご自身の体調や生活に合わせて、安全に服用するための知識を一緒に確認していきましょう。
効果的な服用のタイミングと期間の目安
漢方薬は、飲むタイミングが効果を左右することがあります。 清暑益気湯の効果をしっかり引き出すための、基本的な飲み方と期間の目安は以下のとおりです。
【効果的な服用のタイミング】
- 食前
- 食事をする約30分前
- 食間
- 食事と食事の間の空腹時(食後2時間くらいが目安)
一般的に漢方薬は、おなかが空っぽの時に飲むことで、薬の成分がスムーズに体に吸収されやすいといわれています。 そのため、胃の中に食べ物が入っていない食前や食間での服用がすすめられています。
【服用の期間について】 効果があらわれるまでの期間には個人差があり、目的によっても大きく異なります。
夏バテによる倦怠感や食欲不振のような一時的な症状の場合、数日から数週間で効果を感じられることが多いです。 しかし、症状が良くなったからといって、自己判断で服用を中止したり、飲み続けたりせず、一度医師に相談することが大切です。
一方で、清暑益気湯は体質改善の目的で、長期間にわたって使われることもあります。 ある研究では、季節に関係なく長引く咳や息切れに悩む気管支喘息の患者さんに清暑益気湯を処方したところ、良い結果が報告されました。 この研究では、1年以上にわたって服用を続けても、喘息発作が減るなどの有効性が持続したとされています。
このように、目的によって服用期間は大きく変わるため、医師の指示にしっかりと従いましょう。
知っておきたい副作用と飲み合わせの注意
清暑益気湯は比較的安全性の高いお薬ですが、まれに副作用が起こる可能性や、飲み合わせに注意が必要な場合があります。 体に優しいイメージのある漢方薬でも、体質に合わないこともあります。
安心して服用を続けるために、以下の点を知っておきましょう。
【注意したい副作用のサイン】 もし、以下のような症状があらわれた場合は、副作用の可能性があります。 すぐに服用を中止して、医師や薬剤師に相談してください。
| 副作用の種類 | 主な初期症状 |
|---|---|
| 偽アルドステロン症 | ・手足がだるい、しびれる、つっぱる感じがする ・体に力が入らない、筋肉が痛む ・体がむくむ、血圧が高くなる |
| ミオパチー | ・筋肉の痛み、力が入らない(脱力感) |
| 過敏症 | ・皮膚にブツブツができる(発疹)、赤くなる、かゆみが出る |
| 消化器症状 | ・食欲がない、胃がムカムカする、吐き気、下痢 |
特に注意が必要な「偽アルドステロン症」とは、薬の影響で体からカリウムという大事なミネラルが失われ、体に塩分と水分がたまりやすくなる状態のことです。
【飲み合わせの注意】 清暑益気湯には「甘草(カンゾウ)」という生薬が含まれています。 実は、風邪薬や胃腸薬など、市販薬を含めた他の多くの漢方薬にも、この甘草が含まれていることがあります。
甘草の1日の摂取量には目安があります。 複数の漢方薬を一緒に飲むと、知らず知らずのうちに甘草を摂りすぎてしまい、先ほど説明した偽アルドステロン症などの副作用が起こりやすくなることがあるのです。 普段から他のお薬やサプリメントを飲んでいる方は、必ず医師や薬剤師に伝えるようにしてください。
妊娠中・授乳中の方や子ども・高齢者の服用について
妊娠中や授乳中の方、またお子さんやご高齢の方が清暑益気湯を服用する際には、特に慎重な判断が求められます。 自己判断で服用を始めることはせず、必ず事前に医師へご相談ください。
【妊娠中・授乳中の方】 妊娠中や授乳中の服用に関する安全性は、まだ十分に確立されていません。 お母さんの体を通してお腹の赤ちゃんや母乳に影響する可能性がゼロではないため、基本的には服用を避けることが望ましいです。
ただし、医師が治療によって得られるメリットが、考えられるリスクを上回ると判断した場合には、慎重に処方されることがあります。
【お子さん】 お子さんへの使用経験はまだ少なく、安全性が確立していません。 子どもは「大人のミニチュア」ではありません。体の仕組みが違うため、大人と同じ薬をただ量を減らして飲ませるのは大変危険です。 お子さんの年齢や体重、体質に合わせた細かい量の調整が必要になるため、必ず専門家である医師の診察のもとで処方を受けてください。
【ご高齢の方】 ご高齢の方は、一般的に肝臓や腎臓などの機能が、若い頃に比べて少しずつ低下していることが多いです。 そのため、お薬の成分を分解したり、体の外に排出したりする力が弱くなっている傾向があります。 お薬の成分が体に残りやすくなることで、副作用があらわれやすくなる可能性も考えられます。 特に、血圧の上昇やむくみといった症状には注意が必要です。
胃腸が弱い方や持病(高血圧・糖尿病など)がある場合の注意点
もともと胃腸が弱い方や、高血圧などの持病をお持ちの方は、清暑益気湯を服用する際にいくつか注意すべき点があります。 安全な治療のために、ご自身の体の状態を医師に正確に伝えることがとても重要です。
【胃腸が弱い方】 清暑益気湯は、弱った胃腸の働きを助ける漢方薬です。 実際、お腹の診察で、みぞおちのあたりに不快感や抵抗感(漢方では心窩部不快感や心下瘤鞭といいます)がみられる方に処方して、良い効果が得られたという報告もあります。
しかし、もともと胃腸がデリケートな方が食前などの空腹時に服用すると、胃に負担を感じることがあります。 そのような場合は、食後に服用することで症状が和らぐこともありますが、自己判断で飲み方を変えず、まずは医師や薬剤師に相談してみましょう。
【持病(高血圧・糖尿病など)がある方】 以下のような持病がある方は、清暑益気湯の服用によって症状に影響が出る可能性があるため、必ず服用前に医師に相談してください。
- 高血圧、心臓病、腎臓病の方
- 副作用である偽アルドステロン症は、血圧を上昇させたり、体に水分をため込んだりすることがあります。もともとこれらの病気をお持ちの方は、病気のコントロールを難しくしてしまう恐れがあるため特に注意が必要です。
- 糖尿病の方
- 直接血糖値に大きな影響を与えることは少ないとされています。しかし、体調管理の一環として、服用しているお薬はすべて医師に伝えておきましょう。
- 甲状腺の病気がある方
- 甲状腺機能亢進症などがある方は、動悸などの症状が悪化する可能性も考えられます。
持病の治療で他のお薬を飲んでいる場合、飲み合わせの問題も考えられます。 当院では、患者さん一人ひとりの体質や病状を総合的に判断して、最適な漢方薬治療を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
清暑益気湯は当院で処方可能
「毎年、夏になると体がだるくて何もやる気が起きない」 「食欲がなくて、そうめんのような冷たいものしか食べられない」 「暑さのせいで、仕事や家事にまったく集中できない」
夏の厳しい暑さは、心と体に大きな負担をかけます。 そんなつらい季節の不調でお悩みの方に、漢方薬「清暑益気湯」は心強い味方になってくれるかもしれません。
当院では、患者さん一人ひとりの症状や体質を丁寧に診察し、清暑益気湯をはじめとする漢方薬を処方しています。
- あなたに合った漢方薬の選択
- 医療用漢方薬と市販薬の違いを理解し、最適な治療を選びます。
- 西洋と東洋の視点を合わせた総合的な診察
- 症状の裏に隠れた本当の原因を見つけ出します。
- 夏に負けない体質を目指す生活アドバイス
- お薬の効果を高め、根本的な体質改善を目指します。
医療用漢方薬と市販薬の違いと保険適用の可否
「漢方薬はドラッグストアでも売っているけど、何が違うの?」 このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 クリニックで処方される医療用漢方薬と、市販薬には明確な違いがあります。
| 項目 | 医療用漢方薬(クリニックで処方) | 市販薬(ドラッグストアなど) |
|---|---|---|
| 処方 | 医師の診察と処方箋が必要 | 処方箋なしで誰でも購入可能 |
| 成分量 | 病気の治療に必要な有効成分がしっかりと含まれる | 効き目が比較的おだやかなものが多い |
| 保険適用 | 医師が必要と判断すれば保険が使える | 保険適用外(すべて自己負担) |
| 目的 | 病気や症状の治療 | 軽い症状のセルフケア、健康維持 |
医療用漢方薬の最も大きなメリットは、医師があなたの体を診察し、その症状や体質に本当に合ったお薬を選べる点です。 また、治療として認められれば健康保険が適用されるため、費用負担を抑えることができます。 例えば3割負担の方なら、お薬代の支払いは本来の価格の3割で済みます。
一方で、市販薬は手軽に買える便利さがありますが、ご自身の判断で選ぶため、そのお薬が体質に合っていなかったり、症状の本当の原因に対処できていなかったりする可能性も考えられます。 つらい症状をしっかり治したい方、ご自身の体質に合った漢方薬を見つけたい方は、ぜひ一度クリニックにご相談ください。
夏に負けない体質を目指す食事・生活習慣のアドバイス
清暑益気湯はつらい症状を和らげるのに非常に役立ちます。 しかし、お薬だけに頼るのではなく、毎日の生活習慣を見直すことが、夏に負けない丈夫な体をつくるための本当の近道です。
ぜひ、今日からできるセルフケアを試してみてください。
【今日からできる!夏バテ予防セルフケア・チェックリスト】
- 食事のポイント
- □ アイスや冷たいジュースなど、体を冷やしすぎるものの摂りすぎに注意する。
- □ きゅうり、トマト、スイカなど、体の余分な熱を冷ましてくれる夏野菜を食事に取り入れる。
- □ しょうが、みょうが、しそなど、胃腸の働きを助ける薬味を上手に活用する。
- □ 食欲がなくても、豆腐や鶏むね肉、卵など、元気の源になるタンパク質を少しずつ摂るように心がける。
- 水分の摂り方
- □ 「のどが渇いた」と感じる前に、こまめに水分を補給する(常温の水や麦茶がおすすめです)。
- □ コーヒーや緑茶、アルコールは、おしっこを増やす作用があるので飲みすぎない。
- 生活の工夫
- □ ぬるめのお風呂にゆっくり浸かり、体の芯の疲れをリセットする。
- □ エアコンの冷たい風が直接体に当たらないようにし、設定温度を下げすぎない(28℃が目安です)。
- □ 朝や夕方の涼しい時間帯に、軽い散歩などで心地よい汗をかく習慣をつける。
これらの小さな工夫を続けることが、お薬の効果を高め、根本的な体質改善へとつながります。 診察の際には、あなたに合った具体的な方法を一緒に考えていきましょう。
わだ内科・胃と腸クリニックへのアクセス
「清暑益気湯についてもっと詳しく知りたい」「自分の夏バテの原因はなんだろう?」 このようにお感じになった方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
| クリニック名 | わだ内科・胃と腸クリニック |
|---|---|
| 診療科目 | 内科・消化器内科・内視鏡検査・肝臓内科・外科・整形外科・リハビリテーション科 |
| 所在地 | 〒870-0945 大分県大分市津守176番1号 |
| 電話番号 | 097-567-5005 |
| 診療時間 | 月・火・水・金: 8:30-12:00 / 14:00-17:30 木・土: 8:30-12:00 |
| 休診日 | 日曜・祝日、木曜・土曜午後 |
【アクセス】
- お車でお越しの方
- クリニック敷地内に広い駐車場(13台以上)をご用意しております。
【ご予約について】 お電話またはインターネットでご予約いただけます。 ご予約なしでも受診可能ですが、お待ちいただく時間を短くするため、事前の予約をおすすめしております。
まとめ
今回は、夏のつらい不調に役立つ漢方薬「清暑益気湯」について詳しく解説しました。
清暑益気湯は、汗とともに失われたエネルギー(気)とうるおいを補い、体にこもった熱を冷ますことで、夏バテによるだるさや食欲不振、下痢といった症状を和らげてくれます。
「いつもの夏バテだから」と自己判断で市販薬を選ぶ前に、一度専門家にご相談ください。漢方薬は、ご自身の体質に合ったものを選ぶことが何よりも大切です。当院では、丁寧な診察を通じてあなたに最適な漢方薬をご提案します。
つらい夏の不調でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談くださいね。
参考文献
清暑益気湯が奏効した気管支喘息の3症例