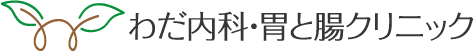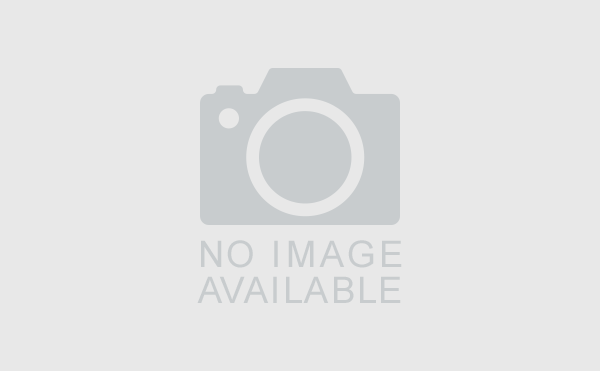柿の食べ過ぎで胃に石ができる?胃石とは?
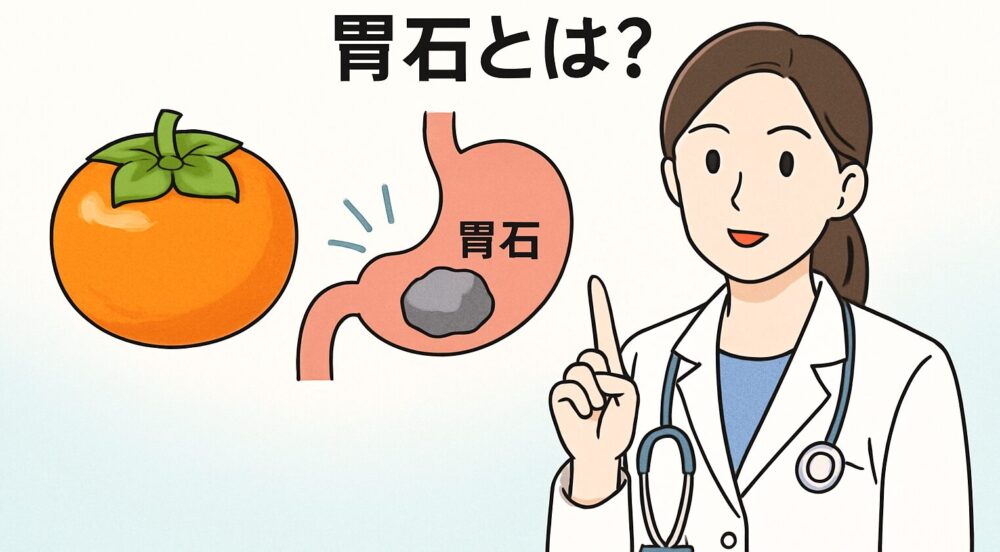
大分県大分市のわだ内科・胃と腸クリニック院長の和田蔵人(わだ くらと)です。秋の味覚として親しまれている柿ですが、その食べ過ぎが原因で胃の中に石ができてしまう可能性があることをご存知でしょうか。「ただの食べ過ぎだろう」と軽く考えているその不調、もしかしたら危険な病気のサインかもしれません。
驚くことに、日本で報告される胃石のうち約7〜8割が柿を原因とする「柿胃石」なのです。放置すると胃潰瘍や腸閉塞(イレウス)といった、緊急手術が必要になるほどの深刻な事態を招くこともあります。
この記事では、なぜ美味しい柿が石に変わるのか、そのメカニズムとリスクが高い方の特徴、そして見逃してはいけない初期症状について、消化器内科の医師が詳しく解説します。ご自身の体調と照らし合わせ、正しい知識で胃の健康を守りましょう。
柿で胃石ができる3つの理由と主な症状
秋になると美味しくなる柿ですが、食べ過ぎが原因で胃の不調を招くことがあります。 「ただの食べ過ぎだろう」と思っていたら、実は胃の中に石ができていた、というケースも少なくありません。
この病気は「胃石(いせき)」と呼ばれ、特に柿が原因でできるものを「柿胃石(かきいせき)」と言います。 ここでは、なぜ柿で胃石ができるのか、その仕組みやできやすい方の特徴、そして見逃すべきではない体のサインについて、消化器内科の医師が詳しく解説します。 ご自身の体調と照らし合わせながら、胃石への理解を深めていきましょう。
胃石とは?胃の中で食べ物が石のように固まる病気
胃石とは、胃の中で食べ物のカスなどが消化されずに絡み合い、長い時間をかけて石のように硬くなった塊のことです。 胃石にはいくつか種類がありますが、植物の繊維が原因となる「植物胃石」が最も多く見られます。
驚くことに、日本で報告される胃石のうち、約7割から8割が柿を原因とする「柿胃石」なのです。 胃石自体の年間発症率は1%未満と比較的稀な病気ですが、決して軽く考えてはいけません。 胃石が大きくなると、以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。
- 胃の出口を塞ぐ 胃から十二指腸への出口を塞いでしまい、食べ物の流れが滞ります。 その結果、腹痛や吐き気、嘔吐といった症状が現れます。
- 胃の粘膜を傷つける 硬い石が胃の壁を傷つけ、胃潰瘍を引き起こすことがあります。 潰瘍から出血したり、まれに胃に穴が開いたりすることもあります。
- 腸に流れて詰まる 胃石が小腸へ移動して詰まると、「腸閉塞(イレウス)」という状態になります。 これは激しい腹痛や嘔吐を伴い、緊急手術が必要になることもある危険な状態です。
胃石は小さいうちは無症状のことが多いため、ご自身で気づくのは困難です。 しかし、お腹の不調が続く場合は、専門の医療機関で原因を調べることが重要になります。
柿の成分「シブオール」が胃酸と反応して固まる仕組み
では、なぜ美味しい柿が、胃の中で石に変わってしまうのでしょうか。 その鍵を握るのは、柿の渋みの元である「シブオール」というタンニンの一種です。
柿胃石は、胃の中で以下のような化学反応を経て作られます。
- シブオールと胃酸の出会い 柿を食べると、渋み成分のシブオールが胃の中に入ります。 胃の中では、食べ物を溶かすために強力な酸である「胃酸」が分泌されています。
- 化学反応による性質の変化 シブオールは胃酸に触れると化学反応を起こし、水に溶けにくい硬い物質に変わります。
- 他の食べ物を巻き込んで巨大化 性質が変わったシブオールは、柿自体の繊維や他の食べ物のカスを接着剤のようにくっつけます。 これが雪だるま式にどんどん大きくなり、石のように硬い塊(柿胃石)を形成するのです。
特に、空腹の状態で柿を食べると、胃の中は胃酸の濃度が高い状態にあります。 そのため、この化学反応がより活発に起こりやすくなると考えられています。 甘柿にもシブオールは含まれていますので、美味しいからといって一度にたくさん食べるのは控えましょう。
胃の手術歴や糖尿病など胃石ができやすい方の特徴
同じように柿を食べても、胃石ができやすい人とそうでない人がいます。 ご自身が以下の特徴に当てはまるか、一度確認してみてください。
| リスクが高い方の特徴 | なぜリスクが高まるのか |
|---|---|
| 1. 胃の手術歴がある方 (特に胃の一部を切除した方) | 胃潰瘍などで胃の一部を切除する手術を受けると、胃の形が変わります。 食べ物を腸へ送り出す動き(蠕動運動)が弱まり、食べ物が胃に停滞しやすくなります。 ある研究では、胃切除術を受けた方の約40%が胃石による腸閉塞を起こしたとの報告もあります。 |
| 2. 糖尿病をお持ちの方 | 血糖値が高い状態が続くと、神経に障害が出ることがあります。 胃の働きを調節する自律神経が影響を受けると、胃の動きが悪くなる「胃不全麻痺」という状態になり、食べ物を排出しにくくなります。 |
| 3. ご高齢の方 | 加齢に伴い、胃の運動機能や消化能力が自然と低下する傾向にあります。 唾液の分泌量も減るため、食べ物を十分に噛み砕けず、消化しにくくなることも一因です。 |
| 4. 早食いやよく噛まない習慣がある方 | 食べ物が大きい塊のまま胃に送られると、消化に時間がかかります。 消化されずに残った食べ物が、胃石の核(中心)になりやすくなります。 |
これらの特徴に当てはまる方は、柿を食べる際に特に注意が必要です。 一度に食べる量を控えめにし、ゆっくりとよく噛んで食べることを意識してください。
腹痛、吐き気、食欲不振など見逃せない初期症状
胃石ができてしまった場合、体はどのようなサインを送るのでしょうか。 胃石が小さいうちは無症状のことも多いですが、大きくなると様々な不快な症状が現れます。
【胃石の可能性がある初期症状チェックリスト】
- □ なんとなく胃が重い、みぞおちあたりに鈍い痛みがある
- □ 食べていないのに、お腹が張って苦しい感じがする(腹部膨満感)
- □ 吐き気やむかつきが続く
- □ 実際に食べたものを吐いてしまうことがある
- □ 以前より食欲がわかない
- □ 少し食べただけですぐにお腹がいっぱいになる(早期満腹感)
これらの症状は、胃炎や胃潰瘍、時には胃がんといった他の胃の病気と非常によく似ています。 そのため、「いつもの胃もたれだろう」と自己判断で放置してしまうのは大変危険です。
特に、「秋になって柿をよく食べてから、どうも胃の調子が悪い」と感じる方は、柿胃石の可能性を考える必要があります。 症状を放置すると、胃石が腸に流れて激しい腹痛や嘔吐を伴う腸閉塞(小腸イレウス)を引き起こすこともあります。 気になる症状があれば、決して我慢せず、お早めに消化器内科にご相談ください。
胃石を診断するための2つの検査法
「柿をよく食べてから胃の調子が悪い」「もしかして胃石?」とご不安な方もいるでしょう。 胃の不快な症状の原因を正確に見つけ、適切な治療につなげるには専門的な検査が欠かせません。 症状だけで自己判断せず、検査で胃の中の状態を確かめることが、回復への最も確実な一歩です。 ここでは、胃石の診断で中心となる2つの検査法について、医師の視点から詳しく解説します。

胃石の確定診断に最も有効な胃カメラ(内視鏡検査)
胃石の診断において、最も確実で多くの情報が得られるのが胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)です。 口や鼻から細いカメラを挿入し、食道から胃、十二指腸の内部までを直接モニターで観察します。
胃カメラ検査が確定診断に最も有効な理由は、以下の3点です。
- 胃石の状態を直接観察できる 胃石の有無はもちろん、大きさや形、色、硬さといった性質まで詳細に確認できます。 これにより、ほぼ100%に近い精度で胃石の診断が可能です。
- 成分を調べて確定診断できる 検査中に胃石の一部を少量採取し(生検)、顕微鏡で詳しく調べることができます。 柿の繊維などが含まれていることを確認し、柿胃石であるという確定診断につながります。
- 診断と治療を同時に行える可能性がある 胃カメラは診断だけでなく、治療にも応用されています。 例えば、比較的小さな胃石であれば、鉗子(かんし)という器具で砕いて取り除くことも可能です。
最近では、内視鏡を用いて胃石に直接コカ・コーラⓇを注入する治療法も報告されています。 胃石は年間発症率が1%未満と稀な病気ですが、これまでは治療のために大量のコカ・コーラⓇを飲んだり、鼻からチューブを入れて洗浄したりする必要がありました。 しかし、内視鏡で直接注入する方法なら、330ml程度の少ない量で石を柔らかくし、安全かつ短時間で砕いて取り除くことが期待できます。 このように、胃カメラは胃石の診断から治療方針の決定まで、非常に重要な役割を担う検査なのです。
鎮静剤を使用した当院の苦しくない胃カメラ検査
「胃カメラは苦しい」「オエッとなるのが怖い」というイメージから、検査をためらってしまう方も少なくありません。 当院では、患者さんに心身の負担なく検査を受けていただけるよう、鎮静剤を使用した苦痛の少ない胃カメラ検査を積極的に行っています。
鎮静剤を使うことで、以下のようなメリットが期待できます。
- うとうとと眠っているような感覚で検査が終わる 点滴から鎮静剤を投与すると、リラックスしてウトウトした状態になります。 多くの方が「気づいたら検査が終わっていた」と感じるほど、楽に受けていただけます。
- つらい嘔吐反射(えずき)を大幅に軽減できる カメラがのどの奥に触れることで起こる不快な反射を、鎮静剤の力で抑えることができます。 これにより、検査中の苦しさが格段に和らぎます。
- より精密で正確な検査につながる 患者さんがリラックスしていると、胃の動きが穏やかになります。 そのため、医師は胃の隅々までじっくりと時間をかけて観察でき、小さな病変の見逃しを防ぎます。
検査後は、鎮静剤の効果が自然に覚めるまで、専用のリカバリールームでゆっくりお休みいただきます。 これまでの胃カメラ検査でつらい経験をされた方や、初めての検査で不安が強い方も、どうぞ安心して当院にご相談ください。
レントゲン検査やCT検査でわかること
胃カメラの他に、診断の補助としてレントゲン検査やCT検査を行うこともあります。 これらの画像検査は、胃石そのものだけでなく、お腹全体の状況を把握するのに役立ちます。
レントゲン検査(腹部単純X線検査) お腹にX線を当てて撮影する、最も基本的な画像検査です。 胃石によって食べ物の流れが滞ると、胃の中に空気と液体の境界線が見えることがあります。 これは腸閉塞の兆候を示唆する所見ですが、胃石そのものがはっきりと写らないことも多いです。
CT検査 X線を使って体の断面図を撮影する、より精密な画像検査です。 CT検査では、胃石の大きさや胃の中での正確な位置を立体的に把握できます。 また、胃石が胃の壁を傷つけていないか、他の臓器に影響を及ぼしていないかなども評価可能です。 ただし、まれに胃石が腫瘍などの他の病気と見分けがつきにくい場合があり、その際は確定診断のために胃カメラ検査が必須となります。
これらの検査は、胃石の全体像を把握したり、合併症の有無を確認したりするために有用です。 しかし、胃石の存在を確実に診断するには、やはり胃カメラによる直接の観察が最も重要と言えます。
胃炎や胃潰瘍など胃石と間違いやすい他の病気との違い
胃石の主な症状である「みぞおちの痛み」「吐き気」「お腹の張り」は、他の胃の病気でも頻繁に見られます。 症状だけで「いつもの胃もたれだろう」と自己判断してしまうのは大変危険です。 以下に、胃石と症状が似ている代表的な病気との違いをまとめました。
| 病名 | 主な原因 | 症状の出方の特徴 | 診断のポイント |
|---|---|---|---|
| 胃石 | 食べ物(特に柿)の塊 | 食後に症状が悪化しやすい ズーンと重い痛みや張りが続く | 胃カメラで石のような塊を直接確認する |
| 急性胃炎 | 暴飲暴食、ストレス、薬の副作用など | 突然のキリキリとしたみぞおちの痛み、吐き気 | 胃カメラで胃粘膜の広範囲な赤みやただれを確認する |
| 胃潰瘍 | ピロリ菌、非ステロイド性抗炎症薬(痛み止め)など | 空腹時や夜間に痛むことが多い 黒い便(タール便)が出ることがある | 胃カメラで粘膜が深くえぐれた「潰瘍」を確認する |
| 機能性 ディスペプシア | 明確な異常はないが、胃の運動機能や知覚に問題がある状態 | 胃もたれ、早期飽満感(すぐにお腹がいっぱいになる) | 胃カメラなどで潰瘍やがんなどの異常がないことを確認した上で、症状から総合的に診断する |
このように、症状は似ていても、胃の中で起きていることは全く異なります。 原因が違えば、もちろん治療法も変わってきます。 正確な診断を下すためには、胃カメラで胃の粘膜の状態を直接観察し、原因を特定することが不可欠です。 気になる症状が続く場合は、ご自身の判断で様子を見ることなく、ぜひ一度、消化器内科を受診してください。
胃石の代表的な治療法と再発を防ぐ3つのポイント
胃石と診断されると、「手術が必要なのか」「どうやって治すのか」と不安に思われるかもしれません。 ご安心ください。胃石の治療法は、石の大きさや患者さんの状態に合わせて複数の選択肢があります。 ほとんどの場合、体への負担が少ない内視鏡治療で対応可能です。 また、治療後には再発を防ぐための生活習慣も重要になります。 ここでは、代表的な治療法から再発予防のポイントまで、消化器内科の医師が詳しく解説します。
コカ・コーラⓇで石を溶かす内服療法・内視鏡的局注療法
「コカ・コーラⓇで石を溶かす」と聞くと、民間療法のように思われるかもしれませんが、これは医療現場で確立された有効な治療法の一つです。 柿胃石の主成分は、柿の渋み成分「シブオール」と胃酸が結合したものです。 この成分は酸性の液体に溶けやすい性質を持っており、コカ・コーラⓇに含まれるリン酸や炭酸が胃石を分解・軟化させる助けとなります。
治療法には、主に2つの方法があります。
- 内服療法 毎日、一定量のコカ・コーラⓇを飲む方法です。 比較的小さな胃石や、症状が軽い場合に選択されることがあります。
- 内視鏡的局注療法 胃カメラ(内視鏡)を使い、胃石に直接コカ・コーラⓇを注入する方法です。 より少ない量で、効率的に石を溶かすことが期待できます。
胃石は年間発症率が1%未満と比較的稀な病気ですが、これまでの治療では課題もありました。 例えば、コカ・コーラⓇを大量に飲んだり、鼻からチューブを入れて胃を洗浄したりする方法では、治療期間が長くなる傾向がありました。 また、溶けきらなかった石が小腸へ流れて腸閉塞を起こすリスクも懸念されていました。
そこで近年注目されているのが、胃カメラで胃石に直接コカ・コーラⓇを注入する「内視鏡的局注療法」です。 ある報告では、胃の手術歴がある73歳の男性の約8cmの柿胃石に対し、この治療法が実施されました。 その結果、わずか330mlという少量のコカ・コーラⓇで石を十分に柔らかくし、安全かつ短時間で完全に取り除くことができたとされています。 この方法は、従来の治療法の課題を克服し、患者さんの負担を大きく減らせる有効な選択肢として期待されています。
内視鏡(胃カメラ)を使って石を砕き取り出す砕石術
コカ・コーラⓇによる溶解療法で効果が不十分な場合や、石が大きい、硬いといった場合には、胃カメラを使った砕石術が標準的な治療となります。 これは、口から挿入した胃カメラの先端から専用の器具を出し、胃石を直接砕いて取り出す方法です。
【内視鏡による砕石術の流れ】
- 鎮静剤の投与 点滴から鎮静剤を投与し、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で治療を開始します。
- 胃石の観察 胃の中を詳細に観察し、胃石の大きさ、硬さ、位置を正確に把握します。
- 胃石の破砕 胃カメラの先端から、石をつかむ「鉗子(かんし)」や輪っか状のワイヤー「スネア」などを出し、石を少しずつ砕いていきます。
- 胃石の回収 細かくなった石の破片を、専用の器具でつまんで体の外へ取り出します。
この治療法の最大の利点は、お腹を切る手術をせずに胃石を取り除けることです。 そのため、体への負担が少なく、入院期間も短縮できる場合がほとんどです。 前述したコカ・コーラⓇ局注療法で石をあらかじめ柔らかくしておくことで、この砕石術がより安全かつスムーズに行えるようになります。
腸閉塞などを起こした場合に行われる外科手術
ほとんどの胃石は内服療法や内視鏡治療で対応できますが、まれに外科手術が必要になることがあります。 手術が検討されるのは、主に以下のような、命に関わる緊急性の高い状況です。
- 胃石が非常に大きい、または硬い場合 内視鏡の器具では破砕が困難なほど、石が巨大化・硬化してしまったケース。
- 腸閉塞(イレウス)を起こした場合 胃石が胃から小腸へ流れ落ち、腸管を完全に塞いでしまった状態です。激しい腹痛や嘔吐、お腹の張りを引き起こします。 腸閉塞を放置すると、腸の血流が滞って組織が壊死することもあり、緊急手術が必要です。
- 胃穿孔(いせんこう)を起こした場合 硬い胃石が胃の壁を傷つけ続け、ついに穴が開いてしまった状態です。胃の内容物が腹腔内に漏れ出し、激しい腹痛と腹膜炎を引き起こします。
特に、過去に胃潰瘍などで胃の一部を切除する手術を受けた方は注意が必要です。 胃の動きが変化しているため、胃石が小腸へ流れやすく、腸閉塞のリスクが高いことが知られています。 ある研究では、胃切除術を受けた方の約40%が胃石による腸閉塞を起こしたとの報告もあります。 手術は体への負担も大きいため、そうなる前に治療を開始することが何よりも大切です。 我慢できないほどの強い腹痛や吐き気が続く場合は、迷わず医療機関を受診してください。
再発を防ぐための柿の適量と食べ方の工夫
無事に胃石の治療が終わっても、以前と同じ生活習慣を続けていれば再発のリスクは残ります。 特に柿が好きな方は、今後の食べ方を少し工夫するだけで、再発リスクを大きく減らすことができます。 「もう柿は食べられない」と悲観する必要はありません。ポイントを押さえて、秋の味覚を賢く楽しみましょう。
【再発を防ぐための柿の食べ方 4つのポイント】
| ポイント | 具体的な工夫 | なぜ大切か? |
|---|---|---|
| 1. 適量を守る | 1日に食べる量は中くらいのもの1個までを目安にしましょう。 | 胃石の原因となる「シブオール」の摂取量をコントロールするためです。 |
| 2. 空腹時を避ける | 食後のデザートなど、胃に他の食べ物がある時に食べるのがおすすめです。 | 空腹時は胃酸の濃度が高く、シブオールが固まりやすくなるのを防ぎます。 |
| 3. よく噛んで食べる | 一口30回を目安に、意識してよく噛むことが大切です。 | 食べ物を細かくすることで消化が促進され、胃への負担が軽くなります。 |
| 4. 渋柿は避ける | 甘柿を選び、十分に熟してから食べましょう。干し柿も注意が必要です。 | 渋みの元であるシブオールは、未熟な柿や渋柿に特に多く含まれています。 |
これらのポイントは、消化機能が発達途中の小さなお子さんや、加齢により胃の働きが低下しがちなご高齢の方が柿を食べる際にも、ぜひ参考にしてください。
胃の働きを整え胃石を予防する日常生活の注意点
柿の食べ方に気をつけるだけでなく、普段から胃腸を健やかに保つことも、胃石の根本的な予防につながります。 胃の消化機能が正常に働いていれば、食べ物が胃の中に長時間とどまるのを防ぎ、石が形成されにくくなるからです。 日々の生活の中で、以下の点を少し意識してみてください。
【胃の働きを整える生活習慣】
- 食事のポイント
- 規則正しい食事時間 毎日なるべく同じ時間に食事をとり、胃腸の活動リズムを整えましょう。
- バランスの良い食事 消化の良い食べ物を中心に、様々な食品をバランス良く摂取しましょう。
- 腹八分目を心がける 食べ過ぎは胃の運動機能を低下させ、食べ物の停滞を招きます。
- 生活習慣のポイント
- 適度な運動 ウォーキングなどの軽い運動は、自律神経を整え、胃腸の動きを活発にします。
- 十分な睡眠 睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、胃の働きに直接影響します。
- ストレス管理 ストレスは胃酸の分泌や胃の運動を乱す大きな要因です。 自分なりの解消法を見つけましょう。
特に、糖尿病をお持ちの方や、過去に胃の手術を受けた方は、胃の動きが悪くなりやすい傾向があります。 持病の管理をしっかりと行うことが、胃石の予防にも直結します。 気になる症状があれば、「これくらいなら」と我慢せず、些細なことでもお気軽に当院にご相談ください。
まとめ
今回は、柿の食べ過ぎで起こる「柿胃石」について、その原因から治療、予防法まで詳しく解説しました。柿に含まれる成分が原因ですが、決して怖い病気ではなく、食べ方を少し工夫するだけで十分に予防が可能です。
秋の味覚を楽しむ際は、1日1個を目安に、空腹時を避けてゆっくりよく噛むことを忘れないでください。特に、過去に胃の手術をされた方や糖尿病をお持ちの方は注意が必要です。
もし、食後の胃もたれや腹痛など気になる症状が続く場合は、「いつものこと」と自己判断せずに、お気軽に消化器内科へご相談ください。専門家と一緒に原因を見つけ、安心で健やかな毎日を取り戻しましょう。
参考文献
- コカ・コーラⓇ局注療法が奏功した胃石の一例コカ・コーラⓇ局注療法が奏功した胃石の一例 著者: 義山 麻衣, 大西 知子, 前田 有紀, 荒川 丈夫, 飯塚 敏郎, 小泉 浩一