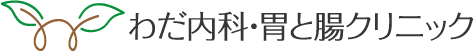原発性胆汁性胆管炎
「原発性胆汁性胆管炎(PBC)」という病名を聞いたことがありますか? あまり馴染みのない病名かもしれません。PBCは肝臓内の胆管が徐々に破壊される進行性の病気で、日本では約5~6万人が罹患していると推定されています。 自覚症状がないまま進行することも多く、早期発見が重要です。 特に50~60歳代の中年女性に多く発症し、かゆみ、疲労感といった初期症状が現れます。 この病気は完治が難しいものの、適切な治療と生活管理によって病気の進行を抑制し、健やかな生活を送ることは可能です。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)を理解する
原発性胆汁性胆管炎(PBC)という病名を初めて耳にする方も多く、難しそうな病名に不安を感じていらっしゃるかもしれません。PBCは、肝臓の小さな胆管が徐々に壊れていく病気です。
胆管は、肝臓で作られた胆汁という消化液を十二指腸に運ぶための管です。この胆管が壊れると、胆汁がスムーズに流れなくなり、体に様々な影響が出てきます。
PBCはゆっくりと進行することが多く、自覚症状がないまま病気が進んでしまうこともあります。そのため、病気が見つかったときには既にかなり進行しているケースも少なくありません。
しかし、適切な治療と生活管理を行うことで病気の進行を遅らせ、症状を和らげ、より長く健やかな生活を送ることが可能です。
この章ではPBCについて、原因や症状、診断、治療法など、基本的な情報をお伝えします。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)とは?
原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、肝臓にある細い胆管に慢性的な炎症が起こり、徐々に破壊されていく自己免疫疾患です。
私たちの体には、細菌やウイルスなど外敵から身を守る免疫システムが備わっています。通常、免疫システムは自分の体の一部を攻撃することはありません。しかし、PBCでは、この免疫システムが誤作動を起こし、自分の胆管を攻撃してしまうのです。
胆管は、肝臓で作られた胆汁を十二指腸に運ぶための管です。胆汁は脂肪の消化吸収を助ける役割を担っています。PBCによって胆管が破壊されると、胆汁の流れが悪くなり、様々な症状が現れます。
以前は原発性胆汁性肝硬変と呼ばれていましたが、近年はPBCという名称が用いられています。
PBCは、大きく分けて症候性PBC(sPBC)と無症候性PBC(aPBC)の2種類に分類されます。sPBCはかゆみ、疲労感、黄疸などの症状が現れます。一方、aPBCは自覚症状がありません。aPBCの場合、健康診断などで偶然発見されることが多く、診断後も無症状のまま経過する患者さんも少なくありません。
どういう病気?原因とメカニズム
PBCは原因不明の慢性進行性疾患です。免疫システムが自分の胆管を異物と認識して攻撃してしまう自己免疫反応が原因と考えられていますが、なぜこのような反応が起こるのか、そのメカニズムは完全には解明されていません。遺伝的要因や環境要因なども関わっている可能性が示唆されています。
PBCでは、抗ミトコンドリア抗体(AMA)、抗gp210抗体などの自己抗体が作られます。これらの自己抗体は、本来自分の体を守るはずの免疫システムが生み出す抗体ですが、PBCでは自分の胆管を攻撃してしまいます。
自己抗体が胆管を攻撃することで炎症が起こり、胆管の破壊につながります。胆管が破壊されると、胆汁の流れが滞り(胆汁うっ滞)、肝臓に胆汁が溜まってしまいます。
この胆汁うっ滞によって、ビリルビンという黄色い色素が血液中に増加し、皮膚や白目が黄色くなる黄疸の症状が現れます。また、胆汁に含まれる成分が皮膚に沈着することで、強い痒みを感じることもあります。
PBCが進行すると、肝臓の線維化が進み、肝硬変へと移行する可能性があります。肝硬変は、肝臓が硬く小さくなってしまう状態で、様々な合併症を引き起こす可能性があります。
どんな人がなりやすいの?:PBCの疫学
PBCは、50~60歳代の中年以降の女性に多く発症します。男性患者さんは全体の1割程度と少なく、女性に多い病気といえます。日本では約5~6万人の患者さんがいると推定されています。
これは、人口約400万人の大分市で考えると、約500~600人の患者さんがいる計算になります。
興味深いことに、欧米諸国に比べると日本の患者数は少なく、ヨーロッパ諸国では日本の3~4倍の有病率が報告されています。なぜこのような地域差があるのかは、まだよくわかっていません。
また、PBCは家族内発症がみられることもあり、血縁者にPBCの患者さんがいる場合は、発症リスクが高まる可能性があると考えられています。
PBCと他の肝疾患との違い:AIH、PSCなど
PBCは他の肝疾患、特に自己免疫性肝炎(AIH)と似た症状を示すことがあり、鑑別が難しい場合があります。AIHも自己免疫疾患であり、肝臓の炎症を引き起こしますが、PBCとは異なり、主に肝細胞が攻撃されます。肝細胞は、肝臓の主要な細胞で、様々な機能を担っています。
PBCとAIHが合併することもあり、PBC-AIHオーバーラップ症候群と呼ばれます。この場合、ウルソデオキシコール酸に加えて、ステロイドなどの免疫抑制剤による治療が必要となることがあります。免疫抑制剤は、免疫システムの働きを抑える薬です。
また、原発性硬化性胆管炎(PSC)も胆管が炎症を起こす病気ですが、PBCとは炎症を起こす胆管の部位や炎症の性質が異なります。PBCは肝臓内の細い胆管が炎症を起こすのに対し、PSCは肝臓の外にある胆管や肝臓内の太い胆管が炎症を起こすことが特徴です。
このように、PBCは他の肝疾患と症状が似ている場合もありますが、原因や病態は異なるため、それぞれの病気の特徴を理解し、適切な検査を受けることが重要です。ご自身の症状や検査結果について、医師とよく相談することが大切です。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)の症状と診断
原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、初期段階では自覚症状が現れにくい病気です。そのため、症状に気づかないまま病気が進行してしまうケースも少なくありません。
早期発見・早期治療のためには、PBCの症状について正しく理解し、少しでも気になる症状があれば、ためらわずに医療機関を受診することが重要です。
主な初期症状:かゆみ、疲労感
PBCの初期症状として最も多く見られるのは、皮膚のかゆみと疲労感です。かゆみは、入浴後や夜間など、体温が上昇する際に強くなる傾向があります。時に我慢できないほど激しいかゆみを感じる場合もあります。かゆみは胆汁に含まれる成分が皮膚に沈着することで生じると考えられていますが、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。
疲労感は、倦怠感や身体のだるさといった漠然とした症状です。この疲労感は、PBCによって肝機能が低下し、体内のエネルギー産生が滞ることによって引き起こされます。かゆみと同様に、疲労感もPBCの進行度合いとは必ずしも関連しません。軽度の疲労感であっても、PBCのサインである可能性があるため、注意が必要です。
これらの初期症状は、他の病気でも見られる一般的な症状であるため、PBCだと気づかないまま放置してしまう方もいらっしゃいます。しかし、PBCは早期に発見し、適切な治療を開始することで、病気の進行を抑制し、QOL(生活の質)を維持することができる病気です。「もしかしたら…」と感じたら、まずは医療機関を受診し、ご相談ください。
進行した場合の症状:黄疸、腹水
PBCが進行すると、黄疸や腹水といった症状が現れることがあります。黄疸は、血液中のビリルビンという黄色い色素が増加し、皮膚や白目が黄色くなる症状です。健康な状態では、ビリルビンは肝臓で処理され、便や尿と一緒に体外へ排出されます。しかし、PBCによって胆管が損傷すると、ビリルビンの排出がスムーズに行われなくなり、血液中に蓄積してしまうのです。
腹水は、お腹の中に水が溜まる症状です。PBCが進行すると、肝臓で作られるアルブミンというタンパク質が減少します。アルブミンは、血液中の水分を血管内に保つ役割を担っているため、アルブミンが減少すると、血管から水分が漏れ出し、お腹に溜まってしまうのです。
その他にも、肝性脳症(意識障害や行動異常)、食道・胃静脈瘤(食道や胃の静脈が拡張し、破裂すると大量出血を起こす可能性がある)、下肢の浮腫などもPBCの進行に伴って現れる可能性があります。
血液検査:抗ミトコンドリア抗体、肝機能検査
PBCの診断には、血液検査が重要な役割を果たします。血液検査では、抗ミトコンドリア抗体(AMA)というPBCに特徴的な自己抗体の有無を調べます。AMAは、PBC患者の約90~95%で陽性となるため、PBCの診断に非常に有用な指標です。
自己抗体とは、本来は細菌やウイルスなどの異物から身体を守るために作られる抗体ですが、PBCでは、この抗体が誤って自分の身体の細胞を攻撃してしまうのです。AMA以外にも、抗セントロメア抗体や抗gp210抗体などの自己抗体がPBCの診断に役立ちます。
また、肝機能検査では、ALP、γ-GTP、ビリルビン、アルブミン、IgMなどの値を測定します。これらの数値から、肝臓の炎症の程度や機能障害の有無を評価することができます。肝機能の状態を把握することで、PBCの進行度合いを判断し、適切な治療方針を決定することが可能になります。
画像検査:超音波検査、MRCP
画像検査では、超音波検査やMRCP(磁気共鳴胆膵管造影)を行います。超音波検査は、肝臓の大きさや形、腹水の有無などを確認するために用いられます。ゼリーを塗った探触子を体に当て、超音波を当ててその反射を画像化します。痛みもなく、体に負担の少ない検査です。
MRCPは、MRI装置を用いて胆管や膵管を描出する検査です。造影剤を使用する場合もありますが、超音波検査と同様に体に負担の少ない検査です。MRCPでは、胆管の狭窄や閉塞の有無などを詳細に評価することができます。これらの画像検査は、PBCの診断だけでなく、他の肝疾患との鑑別にも役立ちます。
肝生検:確定診断のための検査
肝生検は、肝臓組織の一部を採取し、顕微鏡で観察する検査です。肝生検は、PBCの確定診断に必要となる場合があります。局所麻酔を行い、針を刺して肝臓の組織を採取します。 採取した組織を顕微鏡で観察することで、PBCに特徴的な胆管の炎症や破壊の程度を直接確認することができます。
肝生検は、PBCの病期(病気の進行度合い)や病型、活動性の評価にも役立ちます。ただし、血液検査や画像検査の結果からPBCが強く疑われる場合は、肝生検を行わずに診断することもあります。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)の治療と生活
原発性胆汁性胆管炎(PBC)と診断された後は、様々な情報が頭の中を駆け巡り、今後の生活に大きな不安を感じてしまうのも無理はありません。PBCは慢性疾患であるため、生涯にわたる治療が必要となる病気です。しかし、悲観的になる必要はありません。適切な治療と生活管理を続けることで、病気の進行を遅らせ、症状を和らげ、生活の質(QOL)を維持することが十分に可能です。
この章では、PBCの治療法や日常生活での注意点について、詳しくご説明します。PBCとどのように向き合っていけばいいのか、具体的な方法を理解して、少しでも不安を軽減し、前向きな気持ちで治療に取り組めるようにお手伝いできれば幸いです。
ウルソデオキシコール酸(UDCA):PBC治療の第一選択薬
PBCの治療の中心となるのは、ウルソデオキシコール酸(UDCA)という薬です。現在、PBCの治療において最も効果的で安全な薬として広く認識されており、第一選択薬として多くの患者さんに処方されています。
UDCAは、胆汁の流れを良くする作用と肝臓の細胞を保護する作用を併せ持っています。胆汁酸には、本来、脂肪の消化吸収を助ける役割がありますが、PBCによって胆汁の流れが滞ると、この胆汁酸が肝臓にダメージを与えてしまうのです。UDCAは、この胆汁酸の毒性を弱め、肝臓への負担を軽減する働きがあります。胆汁の流れがスムーズになることで、肝臓の炎症を抑え、線維化(肝臓が硬くなること)の進行を遅らせる効果が期待できます。
UDCAの投与量は、欧米では日に体重1kgあたり13~15mgとされています。この量を3回に分けて、毎食後などに服用します。
ただし日本では通常は600mg/日、100mg錠が使用されていますので、1日6錠の内服が基本になります。
UDCAは一般的に安全な薬ですが、副作用として下痢や軟便などがみられる場合があります。これらの副作用は、服用開始後しばらくすると落ち着くことが多いですが、症状が続く場合や強い場合は、医師に相談しましょう。自己判断で服薬を中断することは避けてください。
肝移植:末期PBCの治療選択肢
PBCが進行し、肝機能が著しく低下した場合、肝移植が治療の選択肢となります。肝移植は、健康な肝臓をドナー(提供者)から提供してもらい、患者さんの病気になった肝臓と交換する手術です。肝移植によって、低下した肝機能を回復させ、生活の質を向上させることが期待できます。
肝移植は、大がかりな手術であり、合併症などのリスクも伴います。そのため、肝移植を受けるかどうかは、患者さんの全身状態や年齢、合併症の有無、そしてご本人やご家族の希望を考慮し、専門医と十分に相談した上で慎重に決定されます。
PBCの日常生活の注意点:食事、運動、飲酒
PBCの患者さんは、バランスの取れた食事を摂り、適度な運動を続けることが大切です。肝臓は、栄養素の代謝や貯蔵、有害物質の解毒など、生命維持に欠かせない重要な役割を担っています。そのため、肝臓に負担をかけない食生活を心掛ける必要があります。
アルコールは肝臓に大きな負担をかけるため、摂取は控えましょう。また、脂肪分の多い食事や塩分の多い食事も肝臓に負担をかけるため、注意が必要です。
適度な運動は、肝機能の維持や全身の健康増進に役立ちます。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で継続することが大切です。
PBCは骨粗鬆症のリスクを高めるため、カルシウムやビタミンDを十分に摂取し、日光浴をすることも重要です。かゆみがある場合は、刺激の少ない石鹸を使用し、爪を短く切る、保湿剤を使用するなど、皮膚への刺激を避けるようにしましょう。
規則正しい生活を送り、ストレスをためないようにすることも、PBCの管理には重要です。
わだ内科・胃と腸クリニックでのPBC診療
わだ内科・胃と腸クリニックでは、PBCの診断と治療に当たっています。血液検査、画像検査などを通して、患者さん一人ひとりの状態を正確に把握し、個々の状況に合わせた最適な治療方針を立てています。
また、日常生活の注意点や食事指導、精神的なサポートなど、患者さんの生活の質の向上を目指したきめ細やかな診療を提供しています。PBCは、長期にわたる治療が必要な病気です。わだ内科・胃と腸クリニックでは、患者さんとじっくり向き合い、共にPBCと歩んでいくことを大切にしています。 ご相談やご質問があれば、お気軽にご連絡ください。
まとめ
原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、肝臓の小さな胆管が徐々に壊れていく自己免疫疾患です。中年以降の女性に多く発症し、初期はかゆみ、疲労感など、比較的分かりにくい症状が特徴です。病気が進行すると黄疸や腹水といった症状が現れることもあります。診断には血液検査、画像検査、肝生検などが行われます。
治療の中心はウルソデオキシコール酸(UDCA)の服用です。PBCは慢性疾患であり、生涯にわたる治療が必要ですが、適切な治療と生活管理を行うことで病気の進行を遅らせ、QOL(生活の質)を維持することが可能です。バランスの取れた食事、適度な運動、飲酒制限などを心掛け、規則正しい生活を送りましょう。気になる症状がある場合は、医療機関への相談をおすすめします。
参考文献
- Bhushan S, Sohal A, Kowdley KV. “Primary Biliary Cholangitis and Primary Sclerosing Cholangitis Therapy Landscape.” The American journal of gastroenterology 120, no. 1 (2025): 151-158.
- Jones DEJ, Beuers U, Bonder A, et al. “Primary biliary cholangitis drug evaluation and regulatory approval: Where do we go from here?” Hepatology (Baltimore, Md.) 80, no. 5 (2024): 1291-1300.
- Bolis F, Cazzaniga G, Pagni F, et al. “The phenotypic landscape of primary biliary cholangitis and autoimmune hepatitis variants.” Gastroenterologia y hepatologia 48, no. 2 (2025): 502225.
- Medford A, Childs J, Little A, et al. “Emerging Therapeutic Strategies in The Fight Against Primary Biliary Cholangitis.” Journal of clinical and translational hepatology 11, no. 4 (2023): 949-957.
- Zhang C, Sun G, Jin H, et al. “Double-negative T cells in combination with ursodeoxycholic acid ameliorates immune-mediated cholangitis in mice.” BMC medicine 23, no. 1 (2025): 209.