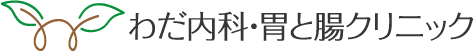肝血管腫
健康診断で「肝血管腫の疑い」という結果を手にし、「腫瘍」という言葉に、がんかもしれないと大きな不安を感じていませんか?そのように心配されるのは、ごく自然なことです。
しかし、どうかご安心ください。肝血管腫は、がんとは全く異なる良性の腫瘍であり、成人の約5%に見られるほど、決して珍しいものではありません。この記事では、がんとの決定的な違いは何か、なぜできるのか、そして「経過観察」と言われたら具体的にどうすればよいのか、皆さまの不安を安心に変えるための正しい知識を、専門医の視点から分かりやすく解説します。
肝血管腫で知っておきたい3つの基本|がんとの違いや症状
健康診断や人間ドックで腹部超音波(エコー)検査を受け、「肝血管腫の疑い」という結果に驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。「腫瘍」と聞くと、多くの方が「がん」を心配されるのは当然のことです。
しかし、肝血管腫はがんと全く異なる良性の腫瘍です。
肝血管腫はがんではない良性腫瘍
肝血管腫は、肝臓にできる腫瘍の中で最も頻繁に見つかるものですが、結論から言うと「がん」ではありません。将来的にがん化することも基本的にないと考えられている「良性腫瘍」です。
これは、肝臓の中にある毛細血管が異常に増え、まるで毛糸玉のように絡まり合って塊(かたまり)になったものです。ほとんどは「海綿状血管腫」と呼ばれる種類で、成人の約5%に見られる、比較的ありふれた腫瘍です。
多くの場合、体に害はなく治療も不要で、経過観察となります。がん(悪性腫瘍)との最も大きな違いは、その性質にあります。
| 項目 | 肝血管腫(良性腫瘍) | 肝細胞がん(悪性腫瘍) |
|---|---|---|
| 増殖の仕方 | 大きくならないか、増大するとしても非常にゆっくりです。 | 無秩序に速く増殖し、周囲の組織を壊しながら広がります。 |
| 転移 | 他の臓器に転移することはありません。 | 血液やリンパの流れに乗り、肺や骨など他の臓器へ転移します。 |
| 体への影響 | 基本的に体に害はありません(巨大なものを除く)。 | 体の栄養を奪い、正常な肝臓の働きを妨げ、命に関わります。 |
このように、肝血管腫とがんは全く異なります。そのため、「肝血管腫がある」と診断されても、過度に心配する必要はありません。まずは正しい知識を持つことが大切です。
肝血管腫ができる原因と大きくなる可能性
肝血管腫がなぜできるのか、そのはっきりとした原因はまだ解明されていません。しかし、生まれつき血管の一部に異常があること(先天的な要因)が関係していると考えられています。
そのため、食生活や飲酒、運動不足といった生活習慣が直接の原因となって発症するわけではありません。
大きさについては、ほとんどの肝血管腫は生涯大きさが変わらないか、大きくなるとしてもそのスピードは非常にゆっくりです。しかし、稀に大きくなるケースも報告されています。
特に、女性ホルモン(エストロゲン)が血管腫の増大に関わっている可能性が指摘されており、以下のような場合は注意が必要です。
- 妊娠 妊娠中は女性ホルモンの分泌が活発になるため、血管腫が大きくなることがあります。
- 女性ホルモン補充療法 更年期障害の治療などで女性ホルモン剤を使用している場合、影響を受ける可能性があります。
- 経口避妊薬(ピル)の服用 ピルの服用で血管腫が明らかに大きくなるという研究結果はありません。しかし、関連を示唆する報告もあるため、服用中の方は医師に伝えておきましょう。
これらの状況に当てはまる方は、定期的な画像検査で大きさの変化を確認していくことがより重要になります。ご自身の状況で気になる点があれば、遠慮なく医師にご相談ください。
基本的に無症状だが破裂時に見られる症状
肝血管腫は、ほとんどの場合、何の症状も引き起こしません。そのため、多くの方が健康診断や人間ドック、あるいは他の病気の検査を受けた際に偶然発見されます。
しかし、腫瘍が非常に大きくなった場合(一般的に直径5cm以上、特に10cmを超えるとリスクが高まる)には、胃や腸など周囲の臓器を圧迫し、症状が現れることがあります。
血管腫が大きくなった場合に見られる可能性のある症状
- お腹の張り(腹部膨満感)
- 右上腹部の不快感や鈍い痛み
- 吐き気、嘔吐
- 食欲不振
また、極めて稀なことですが、お腹を強くぶつけるなどの外傷をきっかけに血管腫が破裂し、腹腔内で大出血を起こすことがあります。破裂した場合は、突然の激しい腹痛や血圧低下、意識障害などが起こります。これは命に関わる危険な状態のため、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
ただし、日常生活で自然に破裂する可能性は非常に低いため、過度に心配する必要はありません。もし上記のような症状に気づいた場合は、放置せずに医療機関を受診してください。
肝細胞がんなど他の肝臓の腫瘍との見分け方
肝血管腫の診断で最も重要なことは、肝細胞がんや転移性肝がんといった「悪性腫瘍」と正確に見分けることです。幸い、近年の画像診断技術の進歩により、体に負担の少ない検査だけで、これらを高い精度で見分けることが可能になりました。
かつては診断を確定するために、お腹に針を刺して組織を採取する「腫瘍生検」が必要な場合もありましたが、現在ではその必要性は大幅に減っています。
見分け方のポイントは、画像検査における血流パターンの違いです。特に、造影剤という薬を注射しながらCTやMRI検査を行うと、腫瘍への血液の流れ方がはっきりと分かります。
| 検査方法 | 肝血管腫の典型的な特徴 | 肝細胞がんの典型的な特徴 |
|---|---|---|
| 超音波(エコー) | 境界がはっきりしていて、白っぽく(高エコーに)見えることが多いです。ただし、この所見だけでは確定できません。 | 様々な見え方をします(モザイク状など)。周囲に「ハロー」と呼ばれる黒い縁が見えることがあります。 |
| 造影CT・MRI | ゆっくりと血液が流れ込みます。造影剤が時間差で辺縁から中心に向かって徐々に染まっていく特徴的なパターンを示します。 | 急速に血液が流れ込みます。造影剤の注入直後に強く染まり、その後すぐに造影剤が抜けていくパターンを示します。 |
このように、専門医がCTやMRIの画像を見れば、その特徴的な血流のパターンから多くの場合、良性か悪性かを判断できます。
また、肝血管腫は肝機能に影響を与えないため、血液検査で肝機能の数値(AST, ALTなど)や腫瘍マーカー(AFP, PIVKA-Ⅱなど)に異常が見られないことも、がんとの鑑別に役立ちます。
肝血管腫の診断に用いる3つの画像検査
健康診断などで「肝血管腫の疑い」と指摘されると、「これはがんなのだろうか」「これからどうなるのだろう」と、多くの方が不安な気持ちになることと思います。
しかし、心配はいりません。近年の画像診断技術の進歩により、体に負担の少ない検査で、肝血管腫と悪性腫瘍(がん)を高い精度で見分けられるようになりました。
診断は通常、段階的に進められます。まずは「腹部超音波(エコー)検査」で病変を見つけ、次に「CT検査」や「MRI検査」といった精密検査で確定診断を目指します。これらの検査を適切に使い分け、肝血管腫の性質を正確に把握することが、皆さまの不要な心配を解消する鍵となります。
健康診断で指摘される腹部超音波(エコー)検査での見え方
腹部超音波(エコー)検査は、体に負担がなく、健康診断などで肝臓の異常を調べる際に最初に行われることが多い、いわば「入口」の検査です。超音波を体に当て、その反響を画像化して内臓の状態を観察します。
肝血管腫は、エコー検査では以下のように見えることが一般的です。
- 境界がはっきりした、丸いかたまりとして見える
- 多くの場合、周囲の正常な肝臓よりも白っぽく(高エコーに)写る
エコー検査は肝血管腫を見つけるのに非常に有用ですが、この検査だけで診断を確定するのは難しいのが現状です。専門的な画像診断のガイドラインでも、エコー検査で見られる「白くて境界がはっきりしたかたまり」という所見だけでは、肝血管腫に特有のものではないとされています。
なぜなら、大きさや場所によっては黒っぽく見えたり、まだら模様に見えたりすることもあり、中には肝細胞がんなどの悪性腫瘍と見分けがつきにくいケースも存在するからです。そのため、エコー検査で肝血管腫が疑われた場合は、より詳しく調べるために精密検査へ進むことが極めて重要になります。
診断を確定する精密検査|CT検査とMRI検査の役割
エコー検査で肝血管腫が疑われた場合、診断を確定させるためにCT検査やMRI検査といった精密検査が行われます。これらの検査は、肝血管腫と他の病気(特に悪性腫瘍)を正確に見分けるために決定的な役割を果たします。
- CT検査 X線を使って体の断面を詳細に撮影する検査です。特に「造影剤」という薬を腕の血管から注射しながら撮影する「造影CT検査」が診断に役立ちます。肝血管腫は血の流れがゆっくりしているため、造影剤を注射すると、腫瘍のふちの部分からゆっくりと染まっていき、時間とともに中心部に向かって徐々に広がっていくという特徴的なパターンを示します。これは、血流が速い肝細胞がんとは明らかに異なるパターンであり、診断の強力な根拠となります。
- MRI検査 強力な磁石と電波を使って体の断面を撮影する検査で、放射線による被ばくの心配がありません。MRI検査は、肝血管腫の診断において非常に精度が高いとされており、多くの専門機関のガイドラインで信頼性の高い確定診断法と位置づけられています。特に「T2強調画像」という撮影方法では、水分を多く含む肝血管腫は白く明るくはっきりと写し出されるという特徴があります。CT検査と同様に造影剤を使ったMRI検査を行うことで、さらに診断の確実性を高めることができます。
| 検査項目 | CT検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 原理 | X線を使用します。 | 強力な磁石と電波を使用します。 |
| 放射線被ばく | あります。 | ありません。 |
| 検査時間 | 比較的短いです(数分~15分程度)。 | 比較的長いです(30分~60分程度)。 |
| 診断のポイント | 造影剤の時間差での染まり方が特徴的です。 | T2強調画像での見え方が特徴的で、診断精度が非常に高いです。 |
| 注意点 | 造影剤アレルギー、腎機能が悪い方などは注意が必要です。 | 閉所恐怖症の方、体内に金属(ペースメーカー等)がある方は受けられない場合があります。 |
造影剤を用いた検査の必要性と安全性
CT検査やMRI検査で使われる「造影剤」は、肝血管腫の診断精度を飛躍的に向上させるために、現在では必要不可欠な薬剤です。造影剤が血管の中を流れることで、臓器や病変の血流の状態を画像上でより鮮明に描き出すことができます。
肝血管腫と肝細胞がんの最も大きな違いの一つが、この「血流のパターン」です。
- 肝血管腫:内部の血流がゆっくりしているため、造影剤は辺縁から中心に向かって、時間をかけて徐々に染まっていきます。
- 肝細胞がん:血流が非常に豊富なため、造影剤を注入した直後に急速かつ全体が強く染まり、その後すぐに造影剤が抜けていきます。
このように、造影剤を用いることで両者の違いが明確になり、正確な診断につながるのです。
もちろん、お薬である以上、副作用の可能性はゼロではありません。主な副作用として吐き気、かゆみ、じんましんなどが挙げられます。安全に検査を受けていただくため、検査前には必ず問診を行い、以下のような点を確認します。
【検査前に医師への申告が必要なこと】
- 過去に造影剤でアレルギー症状(気分が悪くなる、じんましんなど)が出たことがある
- 気管支ぜんそくがある
- 腎臓の機能が悪いと言われたことがある
- アレルギー体質(食べ物、薬など)である
- 特定の糖尿病治療薬を服用している
- 妊娠中、授乳中、またはその可能性がある
これらの項目に該当する場合でも、検査方法を工夫したり、副作用を予防する薬を事前に使ったりすることで、安全に検査を受けられる場合があります。ご不安な点があれば、遠慮なく医師にご相談ください。
大分市の当院で受けられる肝臓の精密検査と専門医による診断
大分市津守にある「わだ内科・胃と腸クリニック」では、健康診断で肝血管腫の疑いを指摘された方への初期診断から、診断後の経過観察まで、責任をもって対応いたします。当院では、高性能な腹部超音波(エコー)検査機器を導入しており、経験豊富な医師が丁寧に検査を行います。
エコー検査の結果、CTやMRIによるさらなる精密検査が必要と判断した場合には、大分市内の高度医療機関と緊密に連携し、患者さんのご都合に合わせてスムーズに検査の予約をお取りしますのでご安心ください。
検査後は、当院の消化器病専門医・肝臓専門医が撮影した画像を患者さんと一緒に見ながら、検査結果を一つひとつ分かりやすくご説明します。「ただ経過観察で良いと言われたけれど、何に気をつければ良いかわからない」といった診断後のご不安にも、専門医の立場から丁寧にお答えします。
肝臓に関するお悩みやご心配なことがありましたら、まずは一度、当院までお気軽にご相談ください。
肝血管腫の経過観察と日常生活における4つの注意点
健康診断などで肝血管腫を指摘され、「経過観察で良い」と言われても、具体的にどうすればよいのか、日常生活で気をつけることはないのか、ご不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
ほとんどの場合、肝血管腫は特別な治療を必要としない良性の腫瘍です。しかし、安心して日々の生活を送るためには、正しい知識を持ち、いくつかの点に注意して付き合っていくことが大切です。
ここでは、経過観察の具体的な内容や、日常生活における注意点を4つのポイントに分けて、医師の視点から分かりやすく解説していきます。
「経過観察」で良いと言われた場合の具体的な検査頻度
「経過観察」と言われた場合、基本的には定期的な腹部超音波(エコー)検査で、血管腫の大きさや形、数に変化がないかを確認していきます。体に負担のない検査で、血管腫の状態を継続的に把握することが目的です。
なぜ定期的な検査が必要かというと、ほとんどの肝血管腫は生涯大きさが変わらない一方で、ごく稀に大きくなるケースがあるためです。そのわずかな変化を早期に捉えるために、経過観察は非常に重要です。
検査の頻度は、患者さん一人ひとりの状態によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 基本的な頻度 年に1回の腹部超音波(エコー)検査を行います。
- より頻繁な検査が推奨される場合 以下のようなケースでは、半年に1回など、より短い間隔での検査をご提案することがあります。
- 発見された血管腫のサイズが大きい(例: 直径5cm以上)
- 血管腫の数が多い
- 過去の検査で大きくなっている傾向が見られる
- 妊娠を考えている、あるいはピルを服用している
- 脂肪肝や慢性肝炎など、肝臓に他の病気がある
大切なのは、ご自身の判断で検査をやめてしまわず、医師の指示に従ってきちんと経過を見ていくことです。定期的な検査で変化がないことが確認できれば、過度に心配する必要はありません。ご自身の検査頻度に疑問があれば、遠慮なく医師にご相談ください。
食事・飲酒・運動(筋トレ)が肝血管腫に与える影響
肝血管腫があると診断されても、日常生活を過度に制限する必要はありません。食事や運動が肝血管腫を直接大きくしたり、悪化させたりするという明確な医学的根拠は、現在のところありません。
- 食事について 特定の食べ物が血管腫に影響を与えることはありません。しかし、肝臓全体の健康を保つために、バランスの取れた食事を心がけることは非常に重要です。脂肪分の多い食事や糖分の過剰摂取は、脂肪肝の原因となり肝臓に負担をかけます。肝血管腫とは別の肝臓の病気を予防する意味でも、健康的な食生活を送りましょう。
- 飲酒について 適量のアルコールであれば、基本的に問題ありません。しかし、過度な飲酒はアルコール性肝障害など、肝臓に大きなダメージを与える原因となります。これは肝血管腫の有無にかかわらず言えることです。休肝日を設けるなど、節度ある飲酒を心がけましょう。
- 運動(筋トレ)について ウォーキングやジョギング、一般的な筋力トレーニングなどの運動は、全く問題なく行えます。ただし、巨大な血管腫(直径10cmを超えるなど)がある場合は注意が必要です。お腹に強い衝撃が加わる可能性のあるスポーツ(例: ラグビー、柔道、ボクシングなど)は、稀なケースですが破裂のリスクを考慮し、避けた方が安全な場合があります。運動習慣について不安な点があれば、事前に主治医に確認しましょう。
ピルの服用や妊娠・出産を考えている方の注意点
肝血管腫は、女性ホルモン(エストロゲン)の影響で大きくなる可能性が指摘されています。そのため、低用量ピル(経口避妊薬)の服用や、妊娠・出産を考えている女性は、特に丁寧な経過観察が必要です。
- ピルの服用を考えている、または服用中の方 ピルの服用によって、必ずしも血管腫が大きくなるわけではありません。関連を示唆する報告はありますが、明確な因果関係は証明されていません。大切なのは、ピルを処方してもらう婦人科医と、肝血管腫を診てもらっている消化器内科医の両方に、ご自身の状況を正確に伝えておくことです。服用中は、通常よりもこまめに腹部超音波(エコー)検査を行い、血管腫の大きさに変化がないかを確認していくことが推奨されます。
- 妊娠・出産を考えている方 妊娠中は女性ホルモンの分泌量が大きく変動するため、肝血管腫が増大する可能性があります。そのため、妊娠を計画している段階で、一度かかりつけの医師に相談することが重要です。妊娠前のサイズを正確に把握しておくことで、妊娠中の変化を正しく評価できます。妊娠中も、お腹の赤ちゃんに影響のない腹部超音波(エコー)検査を定期的に行い、慎重に経過を観察していきます。
治療が必要となるケース(増大や症状の出現)と治療法
ほとんどの肝血管腫は生涯にわたって治療を必要としませんが、ごくまれに治療が検討される場合があります。日本医学放射線学会のガイドラインでも、治療の対象となるのは主に以下のようなケースとされています。
- 腹痛などの症状がある場合 血管腫が大きくなり、周囲の臓器を圧迫することで、みぞおちの痛み、お腹の張り、吐き気などの症状が現れた場合。
- 急速に大きくなる場合 定期的な検査で、血管腫が明らかに速いペースで増大していると判断された場合。
- 破裂の危険性がある場合 腫瘍のサイズが非常に大きい場合や、お腹を強くぶつけるなどして破裂した場合、またその危険性が高いと判断された場合。
- 血液の病気を合併した場合 極めてまれですが、巨大な血管腫が原因で血液が固まりにくくなる病気(カサバッハ・メリット症候群)を引き起こした場合。
これらの状況に応じて、以下のような治療法が選択されます。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 肝動脈塞栓術 | 足の付け根の血管からカテーテルという細い管を入れ、血管腫に栄養を送っている動脈を塞ぐ治療法です。体への負担が比較的少ないのが特徴です。 |
| 外科手術 | 血管腫だけを摘出する、あるいは血管腫を含む肝臓の一部を切除する根本的な治療法です。体への負担も考慮し、慎重に適応が判断されます。 |
どの治療法を選択するかは、症状、血管腫の大きさや場所、全身の状態などを総合的に判断して決定します。当院では、もし治療が必要と判断した際には、大分市内の適切な高度医療機関と緊密に連携し、責任をもってご紹介いたしますのでご安心ください。
まとめ
今回は、肝血管腫の基本的な知識から診断、経過観察の方法まで詳しく解説しました。
健康診断などで「肝血管腫の疑い」と指摘されると驚かれるかもしれませんが、これはがんと全く異なる良性の腫瘍です。ほとんどの場合、体に害はなく、将来がん化することもありませんので、過度に心配する必要はありません。
大切なのは、定期的に超音波(エコー)検査などを受け、大きさの変化がないかを確認していくことです。日常生活で食事や運動を厳しく制限する必要もありません。
正しい知識を持つことが、不要な不安を解消する第一歩です。もしご自身の状況で気になることや、診断後の生活でご心配な点があれば、些細なことでも遠慮なく専門医にご相談ください。
参考文献
- 肝海綿状血管腫の画像診断ガイドライン 2007年版